「日本におけるイタリア2001年」の開会を飾る最も重要な展覧会である。フィレンツェのルネッサンスのすごいものがやってきた。
 ラファエロは聖母子像の作家であるといっても過言ではない。この「ヴェールの女」はこれらの聖母子像のいずれにも劣らぬ優れた作品である。ヴェールの柔らかい質感、美しい髪と真珠の髪飾り、愛らしい黒い瞳、瑪瑙のような首飾り、そして金色のテープの縁取りなどすべての人を魅了する美の化身である。
ラファエロは聖母子像の作家であるといっても過言ではない。この「ヴェールの女」はこれらの聖母子像のいずれにも劣らぬ優れた作品である。ヴェールの柔らかい質感、美しい髪と真珠の髪飾り、愛らしい黒い瞳、瑪瑙のような首飾り、そして金色のテープの縁取りなどすべての人を魅了する美の化身である。

ティツィアーノの「フローラ」は教科書にもでてくる有名な作品である。美しい髪、豊かな身体、そして右手に持った花、すべての人を魅了する花の女神である。
フィリッポ・リッピの「王座の聖母子と天使・諸聖人」は上部を切り取られた小品であるが、力強く人々を描き出している。ギルランダイオの「慈悲の聖母」も大きなフレスコ画である。この壁画は幾世紀にもわたって何度も危機にさらされたのだそうであるが、今では壁からはがされ、支持体の上に移され、そして補強や洗浄を加えて、日本にやってきたのである。慈悲の聖母は大きなマントで人々を覆い、励ましている。人々の信心深さが良く伝わってくる。フランチェスカ、マンテェーニャと続々すごい画家の作品が出てくる。ベッリーニの「受胎告知」も静かに落ち着いてよい。
 フラ・アンジェリコの「聖母の結婚」は板絵の小品であるが、美しい衣装に包まれ、それぞれに豊かな表情をたたえている。光背や縫い取りの金の輝きも印象的である。 フラ・アンジェリコの「聖母の結婚」は板絵の小品であるが、美しい衣装に包まれ、それぞれに豊かな表情をたたえている。光背や縫い取りの金の輝きも印象的である。
 ボッチチェルリの「受胎告知」は大きな大きなフレスコ画、よくこんな大きいものを持ってきたと驚く。マリアは室内に、ガブリエルは屋外にいる。きっちりと繊細な感情が出ている。 ボッチチェルリの「受胎告知」は大きな大きなフレスコ画、よくこんな大きいものを持ってきたと驚く。マリアは室内に、ガブリエルは屋外にいる。きっちりと繊細な感情が出ている。
ボッティチェルリの「受胎告知」は天使部分と聖母部分の2枚のフレスコを接ぎ合わせた大作品である。受胎告知といえばサンマルコ修道院のフラ・アンジェリコの作品が有名であるが、どうしてこの作品はそれに引けを取らない優美さと詩情を兼ね備えており、聖母マリアの表情は真に迫っている。大天使ガブリエルの困った顔も印象的である。

 ポライウオーロの「ヘラクレスとヒュドラ」は有名な作品で、しばしば教科書にも載っているものであるが、このような小品であるとは思ってもいなかった。しかしその迫力はすざましく、思わず目を背けたくなるほどである。 ポライウオーロの「ヘラクレスとヒュドラ」は有名な作品で、しばしば教科書にも載っているものであるが、このような小品であるとは思ってもいなかった。しかしその迫力はすざましく、思わず目を背けたくなるほどである。
マザッチョの「くすぐりの聖母」も小さな板絵だったが、聖母マリアが人差し指と中指で幼児キリストのあごをくすぐっているユーモラスな構図である。聖母マリアの青のマントや金地の背景は、古いキリスト教美術を踏襲しているが、キリストがくすぐったがってあごを引いているところなどは非常に新しい感覚である。
(2000.5a)
|
 11月8日に出かけた。 ここでのMOMA展も3回目である。新館増設のため常設展示が日本に疎開するのだという。理由は何であれ、良い作品が日本で観られるのだから、文句を言う筋合いではない。
11月8日に出かけた。 ここでのMOMA展も3回目である。新館増設のため常設展示が日本に疎開するのだという。理由は何であれ、良い作品が日本で観られるのだから、文句を言う筋合いではない。 山手線の大崎駅の駅ビルのようなところに「O美術館」があり、一度行ってみたいと思っていたが、ちょうどこの展覧会があったので覗いてみた。
山手線の大崎駅の駅ビルのようなところに「O美術館」があり、一度行ってみたいと思っていたが、ちょうどこの展覧会があったので覗いてみた。 「カラヴァッジョ生誕430年」と「日本におけるイタリア2001年」を記念しての展覧会。カラヴァッジョは光と影の巨匠として、バロック絵画の先駆者となった画家。確かに背景は真っ黒で、人物に左からまたは右からと光があたっている。光があった所と陰になったところのコントラストがはっきりしていて、明暗法という彼独特の手法だ。人物やその持物などは実にリアリズムに表現している。
「カラヴァッジョ生誕430年」と「日本におけるイタリア2001年」を記念しての展覧会。カラヴァッジョは光と影の巨匠として、バロック絵画の先駆者となった画家。確かに背景は真っ黒で、人物に左からまたは右からと光があたっている。光があった所と陰になったところのコントラストがはっきりしていて、明暗法という彼独特の手法だ。人物やその持物などは実にリアリズムに表現している。
 これも「日本におけるイタリア2001年」の記念展。
これも「日本におけるイタリア2001年」の記念展。 初めて、府中市美術館に行った。府中の森の中にある。
初めて、府中市美術館に行った。府中の森の中にある。 広島へ行ったとき原爆ドームや、平和公園を観光していたらちょうど「シーガル展」をしていたので中に入った。2000年に亡くなったそうだ。生身の人間から直接型を取るというユニークな手法で作った真っ白い等身大の人物石膏像が、しかも街中を歩いていたり、本物のベンチに坐ったいたり、何人かで話していたり、本当の電車の中だったりというように生活の中の一こまのように像があるのだ。
広島へ行ったとき原爆ドームや、平和公園を観光していたらちょうど「シーガル展」をしていたので中に入った。2000年に亡くなったそうだ。生身の人間から直接型を取るというユニークな手法で作った真っ白い等身大の人物石膏像が、しかも街中を歩いていたり、本物のベンチに坐ったいたり、何人かで話していたり、本当の電車の中だったりというように生活の中の一こまのように像があるのだ。 「風景画ができるまで」という副題がつぃいた展覧会である。
「風景画ができるまで」という副題がつぃいた展覧会である。 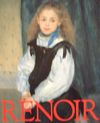 ルノワールは若い女性に人気のある画家である。いつもは空いているブリヂストン美術館だが、今日はさすがに混んでいる。横に並んでいるオバサンに聞くと、わざわざ名古屋から観に来たという。よっぽど早起きして来たに違いない。実はこの展覧会は名古屋市美術館でも2ヶ月後には行われるのであるが、それを待ちきれなかったのか・・・あるいは知らなかったのか。
ルノワールは若い女性に人気のある画家である。いつもは空いているブリヂストン美術館だが、今日はさすがに混んでいる。横に並んでいるオバサンに聞くと、わざわざ名古屋から観に来たという。よっぽど早起きして来たに違いない。実はこの展覧会は名古屋市美術館でも2ヶ月後には行われるのであるが、それを待ちきれなかったのか・・・あるいは知らなかったのか。 これも「日本におけるイタリア年」を記念して行われたもので、18世紀のヴェネチア絵画展である。
これも「日本におけるイタリア年」を記念して行われたもので、18世紀のヴェネチア絵画展である。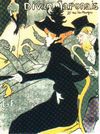 ロートレックは変わった画家です。名家に生まれたが、骨折を繰返し、非常に身長が小さくなってしまい、画家になったのですが、モンマルトルに飛び出していって、芸人や娼婦などの画を好んで描いたと言う放浪の一生でした。
ロートレックは変わった画家です。名家に生まれたが、骨折を繰返し、非常に身長が小さくなってしまい、画家になったのですが、モンマルトルに飛び出していって、芸人や娼婦などの画を好んで描いたと言う放浪の一生でした。 丸紅は日本を代表する商社である。このような商社がボッチチェリのシモネッタという世界の至宝を手にするに至ったいきさつはあまり知りたくない。商社だけに、ビジネスの世界の話が入っているに違いない。
丸紅は日本を代表する商社である。このような商社がボッチチェリのシモネッタという世界の至宝を手にするに至ったいきさつはあまり知りたくない。商社だけに、ビジネスの世界の話が入っているに違いない。 また切符をいただいたので行ってきた。今日はオープニングレセプションといって、特別鑑賞会なのだ。一般より早く観られ、主催者の話などあり、ワインと ちょっとしたおつまみがついて 帰りにはカタログをいただけるのだ。
また切符をいただいたので行ってきた。今日はオープニングレセプションといって、特別鑑賞会なのだ。一般より早く観られ、主催者の話などあり、ワインと ちょっとしたおつまみがついて 帰りにはカタログをいただけるのだ。
 中国6000年の歴史と文化、しかも国宝級のものがやってきた。
中国6000年の歴史と文化、しかも国宝級のものがやってきた。 主人の学会行きに連れ立って福岡に来た。大体の外国の美術館の展覧会は東京で開催されると思っていたが、今回のは福島、大阪、島根と福岡だけである。ちょうど福岡に来れてよかった。ボルドー市と福岡は姉妹都市なのだそうだ。
主人の学会行きに連れ立って福岡に来た。大体の外国の美術館の展覧会は東京で開催されると思っていたが、今回のは福島、大阪、島根と福岡だけである。ちょうど福岡に来れてよかった。ボルドー市と福岡は姉妹都市なのだそうだ。 フォービスムの画家として注目されたマティスはその後いろいろと作風を変遷した。今回は繰り返し描いた女性像に焦点を集めている。
フォービスムの画家として注目されたマティスはその後いろいろと作風を変遷した。今回は繰り返し描いた女性像に焦点を集めている。 泊っていた徳島から大枚をはたいてタクシーに乗って
泊っていた徳島から大枚をはたいてタクシーに乗って
 7月2日に出かけた。やはりマンチェスター美術館のものが中心である。
7月2日に出かけた。やはりマンチェスター美術館のものが中心である。  第3は「女性と恋」。レイトンの「オダリスク」−−ちょっとのぞいた胸が艶めかしい、ワッツの「メイ」−−祈る少女、ロセッティの「あずまやのある草原」−−表情のない女たち、ミレイの「ステラ」−−理知的な女性、ペルジーニの「読書する娘」−−これも結構太め、ムーアの「牧歌」−−はだしの娘が二人、スラドウィックの「林檎は黄金色にて歌声甘美なれど夏すでに過ぎ」−−まだまだお嫁に生ける二人。
第3は「女性と恋」。レイトンの「オダリスク」−−ちょっとのぞいた胸が艶めかしい、ワッツの「メイ」−−祈る少女、ロセッティの「あずまやのある草原」−−表情のない女たち、ミレイの「ステラ」−−理知的な女性、ペルジーニの「読書する娘」−−これも結構太め、ムーアの「牧歌」−−はだしの娘が二人、スラドウィックの「林檎は黄金色にて歌声甘美なれど夏すでに過ぎ」−−まだまだお嫁に生ける二人。 これはラファエル・コラン生誕150年記念の展覧会であるが、なんとこれが彼の世界最初の回顧展である。フランスでは、まったく忘れ去られた画家なのである。
これはラファエル・コラン生誕150年記念の展覧会であるが、なんとこれが彼の世界最初の回顧展である。フランスでは、まったく忘れ去られた画家なのである。





 ポライウオーロの「ヘラクレスとヒュドラ」は有名な作品で、しばしば教科書にも載っているものであるが、このような小品であるとは思ってもいなかった。しかしその迫力はすざましく、思わず目を背けたくなるほどである。
ポライウオーロの「ヘラクレスとヒュドラ」は有名な作品で、しばしば教科書にも載っているものであるが、このような小品であるとは思ってもいなかった。しかしその迫力はすざましく、思わず目を背けたくなるほどである。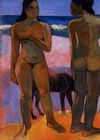

 太平洋に浮かぶ常夏の島。こんな島に文化的な美術館があるとは思わなかった。しかし地元の女性の個人コレクションをもとに創設された美術館だそうだ。
太平洋に浮かぶ常夏の島。こんな島に文化的な美術館があるとは思わなかった。しかし地元の女性の個人コレクションをもとに創設された美術館だそうだ。 シスレーと言うと、風景画だが、今回の展覧会もほとんどが風景画であった。私は、ピサロとシスレーの風景画が見分けにくい。主人いわく「空の面積が多いほうがシスレー」と。確かにそうかも知れない。木の描き方が印象派で風や光を感じさせるもので、時々、主人とドライブをしていて 周りの景色を思わず「シスレーの景色だ!」と叫びあうことがある。美術鑑賞が二人の共通の趣味なので、感情を共有できるのだ。
シスレーと言うと、風景画だが、今回の展覧会もほとんどが風景画であった。私は、ピサロとシスレーの風景画が見分けにくい。主人いわく「空の面積が多いほうがシスレー」と。確かにそうかも知れない。木の描き方が印象派で風や光を感じさせるもので、時々、主人とドライブをしていて 周りの景色を思わず「シスレーの景色だ!」と叫びあうことがある。美術鑑賞が二人の共通の趣味なので、感情を共有できるのだ。
 パリに出てからは、明るい静物画 自画像 風景画になる。「レストランの内部」は部分的に点描で描かれていてすばらしいし,各テーブルに置かれた花もゴージャスで美しい。アルルで描かれたミレーの影響を受けた「種まく人」は黄色の太陽を背に農夫が種をまいている。まくそばから、カラスが何羽か飛んできているのがゴッホらしい。「郵便配達ルーラン」の絵は背景に花がちりばめられていて髭面のルーランにちょっと合わないがそこがまたゴッホらしい。
パリに出てからは、明るい静物画 自画像 風景画になる。「レストランの内部」は部分的に点描で描かれていてすばらしいし,各テーブルに置かれた花もゴージャスで美しい。アルルで描かれたミレーの影響を受けた「種まく人」は黄色の太陽を背に農夫が種をまいている。まくそばから、カラスが何羽か飛んできているのがゴッホらしい。「郵便配達ルーラン」の絵は背景に花がちりばめられていて髭面のルーランにちょっと合わないがそこがまたゴッホらしい。 サンレミ時代は、波打つ感じの線描画となる。オーヴェール時代の「医師ガッシェ」はエッチングで描かれパイプをくわえている姿だ。昔観たのを覚えている絵もあったが、ほとんどは初めてみるものが多かった。クレラーミューラー美術館は主人と私にとって大変思い出深いものである。(1999.11t)
サンレミ時代は、波打つ感じの線描画となる。オーヴェール時代の「医師ガッシェ」はエッチングで描かれパイプをくわえている姿だ。昔観たのを覚えている絵もあったが、ほとんどは初めてみるものが多かった。クレラーミューラー美術館は主人と私にとって大変思い出深いものである。(1999.11t)  スイスには個人コレクションが多いのですが、医師のグスタフ・ロー博士はザイールに病院を作ったり、飢えに苦しむ人に食料を無償で提供したりした人格者ですが、一方美術愛好家でもあり、素晴らしいコレクションを形成している。
スイスには個人コレクションが多いのですが、医師のグスタフ・ロー博士はザイールに病院を作ったり、飢えに苦しむ人に食料を無償で提供したりした人格者ですが、一方美術愛好家でもあり、素晴らしいコレクションを形成している。
 久しぶりにオルセーの名品に接した。1997年に実際にオルセーに行った時には、慌しくて、一品ずつ鑑賞する余裕はなかったので、このように選ばれたものを東京で観られるのは本当に有り難い。
久しぶりにオルセーの名品に接した。1997年に実際にオルセーに行った時には、慌しくて、一品ずつ鑑賞する余裕はなかったので、このように選ばれたものを東京で観られるのは本当に有り難い。 「水の都の炎の芸術」というヴェネチアン・グラスの展覧会。4000年以上の歴史を持つガラスの展覧会は、米国のコーニング・ガラス美術館で観たことがあるが、大分前のことであまり覚えていない。
「水の都の炎の芸術」というヴェネチアン・グラスの展覧会。4000年以上の歴史を持つガラスの展覧会は、米国のコーニング・ガラス美術館で観たことがあるが、大分前のことであまり覚えていない。 ハーバード大学のフォッグ美術館から来た近代絵画である。日本の大学ではこんなに沢山のヨーロッパ絵画を持っているところはないであろう。やはりアメリカの底力か。
ハーバード大学のフォッグ美術館から来た近代絵画である。日本の大学ではこんなに沢山のヨーロッパ絵画を持っているところはないであろう。やはりアメリカの底力か。
 ピカソの有名な「招魂」は、失恋のため自殺した親友カサヘマスへのオマージュであり、青の時代の幕開けの作品である。
ピカソの有名な「招魂」は、失恋のため自殺した親友カサヘマスへのオマージュであり、青の時代の幕開けの作品である。 ダリは天才である。シュールレアリスムの鬼才である。今回の展覧会は米国フロリダにあるサルバドール・ダリ美術館からのものを中心にしたものである。
ダリは天才である。シュールレアリスムの鬼才である。今回の展覧会は米国フロリダにあるサルバドール・ダリ美術館からのものを中心にしたものである。 静物画というジャンルで、20世紀にどう変化していったかが分かる展覧会である。19世紀までのアカデミックなものから、20世紀になるとモダニズムとなる。アメリカのフィリップス・コレクションの所蔵品からのものである。
静物画というジャンルで、20世紀にどう変化していったかが分かる展覧会である。19世紀までのアカデミックなものから、20世紀になるとモダニズムとなる。アメリカのフィリップス・コレクションの所蔵品からのものである。
 主人がアメリカの留学中に、私もこのワシントンギャラリーに行ったはずなのだが、よく覚えていない。もっとも、当時は絵画鑑賞に目ざめていなかったからなのであろう。今あらためて もったいない事をしたものだと思う。
主人がアメリカの留学中に、私もこのワシントンギャラリーに行ったはずなのだが、よく覚えていない。もっとも、当時は絵画鑑賞に目ざめていなかったからなのであろう。今あらためて もったいない事をしたものだと思う。
 再び、エルミタージュからイタリア・ルネサンスの作品が来た。
再び、エルミタージュからイタリア・ルネサンスの作品が来た。
 カタログを買ってきたが、だんだんと大部になり、辞書のようになってきた。とくに前のほうに長い説明や解説がいくつも並んでいるのには閉口する。売れない美術評論家の論文の抱き合わせ商法といわれても仕方あるまい。このような大きなものになると、高齢者には持って帰るのも大変である。それを見越して、ちゃっかりと宅急便がデスクを出している。これも西洋美術館のタイアップ商法かもしれない。何せ独立行政法人ともなれば、今までのように国民の税金を使っているだけでは、倒産の可能性も出てきているからである。それほど世の中の変化のスピードは速い。(1999.3a)
カタログを買ってきたが、だんだんと大部になり、辞書のようになってきた。とくに前のほうに長い説明や解説がいくつも並んでいるのには閉口する。売れない美術評論家の論文の抱き合わせ商法といわれても仕方あるまい。このような大きなものになると、高齢者には持って帰るのも大変である。それを見越して、ちゃっかりと宅急便がデスクを出している。これも西洋美術館のタイアップ商法かもしれない。何せ独立行政法人ともなれば、今までのように国民の税金を使っているだけでは、倒産の可能性も出てきているからである。それほど世の中の変化のスピードは速い。(1999.3a) 世田谷の砧公園は、こども達が小さい時に良く遊ばせに行ったところである。かなり立派な企画展をやるため、何回か足を踏み入れたが、常設展を観たことがなかったので、はいってみた。ほとんど見る人がいなく、これではとても採算がとれないと思った。世田谷区の小学生の展示などもあり、これも地方自治体の役割かなと思ったが、高い区民税を払っているものとしてはなんとも割り切れなかった。これがいわゆるハコモノ行政なのであろう。
世田谷の砧公園は、こども達が小さい時に良く遊ばせに行ったところである。かなり立派な企画展をやるため、何回か足を踏み入れたが、常設展を観たことがなかったので、はいってみた。ほとんど見る人がいなく、これではとても採算がとれないと思った。世田谷区の小学生の展示などもあり、これも地方自治体の役割かなと思ったが、高い区民税を払っているものとしてはなんとも割り切れなかった。これがいわゆるハコモノ行政なのであろう。