���{���p�U�� 06-3�@�i�C�O���p�͕ʃy�[�W�j
| �������̕������W 06.10 | �r�،o�ҁ[�����l���@06.10 | �̐썑�F�@06.10 | �w2006�@06.10 |
| ��]�˓����}���@06.10 | �c���ꑺ�@06.10 | �Y��ʓ��@06.11 | ���{�W�@06.11 |
| UKIYO-E�@06.11 | �R�{�u�l�W�@06.11 | ������{�於��W�@06.11 | �����p���@06.11 |
| �h�炮�ߑ�[���{��Ɨm��̂͂��܂��@06.12 | ���������ߑ���p�ف@��ݓW�@06.12 | �����ƈ����@06.12 | �����������06.12 |
| �������������@06.12 | �ޗǍ����������@06.12 | ��Z���W�@06.12 | ���{�{���p���@06.12 |
| ���s���F���n�旧���p���@06.12 | �R���W�W�F���O�����W���|�C���g 06.12 | �˕������R���N�V�����@06.12 | ��Ép�q�W�@06.12 |
| ���V�V�W�@06.12 | ���t�E�������̎d���@06.12 | ����ƕ����G�Ŋy���ލ]�ˎU���@06.12 | ��菬�ՂƓ��R�@���@06.12 |
�ځ@���@
| ����ƕ����G���y���ލ]�ˎU���F�����Ɖ��̔�����
|
| �@����͍]�ˎ��ォ�瑽���̐l�тƂɐe���܂�Ă���B�o�傪��Ƃ��Ď��R���r��ł���̂ɑ��āA����͐l��̋@����Љ���̖����Ȃǂ����[���A�╗�h�����߂Č��꒲�ʼnr��ł���̂������ł���B �@����̓W���ɂ́A�]�˖����E���E�Ȃ�킢�E�g���E�̕���E�M�E�V�Y�ȂǁA�]�ˎ���̐l�тƂ̕�炵�̈������r�傪��200�_����ł���B����ɂ��Ă͓����Ŕz�z���ꂽ����̉������ǂނƂ悭�����邱�ƂɂȂ��Ă���B
�@���͂����ς畂���G�̊ӏ܂��������̂����A������C�ɂȂ��Ă��������̂ق��ɂ��ڂ������B�W�����ׂ��Ώۂ�����邽�߁A���Ȃ莞�Ԃ�������B�����Ĕ���B�ꏏ�ɍs�����Ɠ��͂��̌�̗\�肪���邽�߂R�O���ŏo�čs�������A�킽���͂R���Ԃ����ĕ����G�̍�҂���������Ƃ߂��肵���B �@����������ƁA�L���ȍL�d�́s�����]�˕S�i�@�l�c�J�����V�h�t���W������Ă���B��̑傫�Ȕn�̋r�̌������ɏh�ꂪ�����Ă����ł���B�����̐���́u�V�h�̎q���͑����w���L���v�ł���B�ē�����ǂނƁA�n���ނƔw���L�т�Ƃ��������܂��ĉr��ł���Ƃ������Ƃ�������Ƃ����d�|���ł���B �@�������B�S�b�z���͎ʂ������ƂŗL���ȍL�d�́s�����]�˕S�i�@�T�˔~�����t�̖T�̐���́A�u�������a�~����T�ւ������v�B���̏ꍇ���~�Ƃ͋T�˂̔~���~�A�T�Ƃ͋T�˓V�_�̗��̂ŁA���t���a�����炱�̂Q���������Ƃ������Ӗ��B����͍L�d�̉�₻�̃^�C�g�����݂�Ή��ƂȂ��z���������A��͂�����������Ă��܂��B �@���������āA�܂����̐���������ɓ���āA�����ǂ�ł����Ă��炱�̓W����ɍs���̂������ł��낤�B���ꗿ�͋͂�100�~�ł��邩��A��p�͖��ł͂Ȃ��B �@���̊��W�͂S�K�ŊJ����Ă������A�Q�K�ɍ~���Ɓu�~�j���R�[�i�[�v�������āA�ّ��̕����G���o�Ă����B�͓�ōւ̔����}�s�Í�����t�A���F�́s�����l�`�@���������Đl�`�̐}�@�����~�̐}�t�Ɓs�ꗬ�ȓƊy�@�|�V�����t�A��ҕs�������N�_�}���ʔ��������B(2006.12a)
|
|
|
||||||||||||||
| �@���V ꎁi���炳�� �ЂƂ��j�̖��O��m�����͍̂ŋ߂̂��Ƃł���B�������p�قŊJ���ꂽ�u���{�{���p�ف[�@�R���N�^�[���u�x�j������20���I���p�v�Ŕ��Ɉ�ۓI�ȓ�̕��V ꎂ̍�i���ς�����ł���B����͑�ڍ��ɃA�_���ƃC����`�����s�_�b�a�t�Ɨ��Ԃ��̐S�����ڂ����Ă��郉�e���ꂪ�����ꂽ�M�s�n�̎M�t�ł������B �@�Ƃ��낪���R�̂��Ƃɕ��V ꎂ̏��߂Ẳ�ړW�����q�ŊJ����Ă���Ƃ�������m�����̂ŁA�Ȃ�Ƃ����Ԃ�s�����ĕW�O���Ɋ��荞�B �@�u�C���[�W�̖��{�ɐ����v�Ƃ����`�e�������V�̏�ɂ��Ă���B��̓W����́u���{�v�Ƃ����L�[���[�h�����L���Ă���̂ł���B
��T�́@�����ؔʼn������̓W����̒��S�ŁA�������Ԕʼn�A�ё��T�|XXX�A���ƕϗe�A����L�A�A���̐����Ȃǂɍו�����Ă����B���̖،��ʼn悪�������Ɗ|�����Ă���W�����ɂ������ނƁA�{���Ɉَ����̐��E�ɘA�ꍞ�܂ꂽ����������B ��U�͂́A�R���[�W���Ő��葹�����ޗ���\��t�������̂Ə����Ă��邪�p���ڂ��܂�����������Ȃ��B ��V�͂́A���[�u���E�I�u�W�F�B���m�̌Ï��𗘗p�������̃R���[�W����{�b�N�X�I�u�W�F�ł��邪�A���V�̕��w�ɑ���X�|���\��Ă���B ��W�͂́A���ʁE�f�`�i�ז���j�ł��邪�A�ނ̋Z�p�̍����������Ă���B��X�͂��n�̍�i�u�a���}�[�u���v�A��Y�͂�����E�����E�}�G�ł���B ���C�ɓ���̍�i�́�
�@�}�^���f���炵���B�{�̑����E������肪����A�[�`�X�g�����ɁA�}�^���̂��̂��A�[�g�ł���B�V��̔ʼn�P�������܂��ŕt���Ă����B (2006.12a) |
| �R���W�W�[���O�����W���|�C���g�F�~�d�}�A�[�g�M�������[
|
|
�@����̓W���͈ӊO�ȃe�[�}�ł���Ƃ������邪�A����͎��̎����O�̃��[���A���_�Ɗϋq��O�������Ȃ��T�[�r�X���_�Ɋ�Â����̂ł��낤�B����ɂ��Ɓu����̍�i�ł͐}����ǂ݉���������X�Ɉӎ����L���āw�G��̌�����x�Ƃ����e�[�}�ɒ��킵���v�Ƃ̂��Ƃł���B���ꂪ����̃��O�����W���|�C���g�Ƃ����W����̈Ӗ��Ȃ̂ł��낤�B (2006.12a) |
| ���s���[��Ƃ����̗��ƕ��i�F���n�旧���p��
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@��Ȗ��ʁE���ʂ̉�Ƃ̖��O��������ƁA���c��i�A���c���v�A������A�c��L���A�ē����O�A�r�c���Y�A����u�l�A�ҏ������A�������A����A�����O�A�R���O�A���c�w�l�A�͈�V���A�c�ӎO�d���A���C���A�ݓS�ܘY�A�쌩�R�Ŏ��A�����h�B �@���̑��ɏ��a�����́u���{�ʼn拦��v���I�u�V���{�S�i�v�̂����P�V�_���o�i����Ă����B���̃V���[�Y�͔��p�o�ŎЂ́u�����G�̗��j�v�ɂ�������Ă��Ȃ����̂ŁA���߂Ă��ڂɂ��������B�w�|���炵�������ɕ����ƁA�u�V���{�S�i�v�̃R���N�V�����͂��̔��p�ق̌ւ肾�Ƃ̂��Ƃł���B��k�╽��̕��i�����{�̕��i�̒��ɓ����Ă��邾���łȂ��A���̑I�蕶���ɂ́u�e��̊�v�E�u���_�v�E�u�ؔŕ��̑������v�Ȃǂ������͂����݂����Ă���B���̂��ߐ푈�L�^��̏ꍇ�Ɠ������A�W�A�̐l�ւ̔������l���Ă��܂���ɂ���Ȃ������̂ł͂���܂����B �@��v�ȍ�i�̓f�[�^�x�[�X�ɒ��쌠��ی삳�ꂽ�摜�Ƃ��Ĕ��p�ق̃z�[���y�[�W�ɃA�b�v����Ă���̂ŁA���L�̊��z�\���烊���N���Ă������B
(2006.12a) |
| ���{�{���p�ف@�R���N�^�[���u�x�j������20���I���p�F�������p��
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�����͂��E�Ƃ݂����̓��j�[�N�Ȑl�ł���B����}���������̂��B���̂���������20���I�A�[�g�𐧍�E�]�_�E�N�W����Ƃ����O�ʘZ�]�̈��C���̂悤�Ȑl�����B1992�N����2001�N�܂őO���s���ŊJ�ق��Ă����u�C�T�n�C�E�x���E�C�}�[�W�����p�فv�ɓW������Ă������u�x�j�̃R���N�V�������獡��o�W����Ă���B �@�ςĂ݂�ƁA���̓W����͑O�q���p�̏W���ł���B�����č�҂̐��������B���̍��u���́u20���I���p�̃E�H�[�L���O�E�f�B�N�V���i���[�v�������̂��Ǝv���B �@�W�������1���́A�C�O��Ƃ̃R���N�V�����A��2���͐푈�Ɖ�Ƃ����A��3���͍�����Ƃ̃R���N�V�����A��������4���͍��u�x�j�̊����ł���B �@��ې[�������̂́A��1���ł̓��H���X�̖т̐������s�S���t�ƒ��F���ꂽ�s�~�����e���t�A�|�X�^�[�̉�ł���T�r�G�́s�I�X�����痈���Ⴂ���t�A���̉e�������A���V���X�L�[�̍�i�A�T���E�t�����V�X�̂��̂ق��͐��s�㕔�̉��F�t�Ȃǂł���B �@��2���ł́A�s�J�\�́s�t�����R�̖��ƉR�t�A�~���̃|�X�^�[�s�X�y�C�����~���t�A�l�c�m���̏��N�����̂Ƃ������ׂ��s���i�t�A��쐽�̌����̑��s�̒��̔��t�ł���B �@��3���ł́A���q�^��Y�́s�o���������t�A���Ԗ퐶�̑傫�ȓ_�`�s��ɖY�ꂽ�X�q�t�A���R�c��Y�́s�����t�A���V�Ă̑�ڍ��ɃA�_���ƃC����`�����s�_�b�a�t�Ɨ��Ԃ��̐S�����ڂ����Ă��郉�e���ꂪ�����ꂽ�M�s�n�̎M�t�ł������B �@��4���̍��u�x�j�̍�i�Ƃ��Ắs�����X�̉��t���ǂ������B�܂��ނ��N���X�g/�W�����k�E�N���[�h�̍����Y�p�̏Љ�҂ł��������Ƃ����߂Ēm�����B (2006.12a) ��Ƃ̐����̂���T�C�g�ւ̃����N
|
|
|
|
�@�Ƃ��낪�������w�t�B���f���t�B�A�u�������v���G�𒆐S�Ɂx�ƌ�������̉��Ɂu��Z���W�v���J����Ă���B�����̐V���j���p�قł͂��̉��G�̍쐬���f���ŏЉ��Ă����B��Z���́u���v�͉E���́u�M�i�_�j�v��������������������A�����ł́u���v�ő�p�����Ă��������B �@�t�B���f���t�B�A�̃t�F�A�����g�������Ɍ������鏑�@����́u�������v��1954�N�ɓ��ėF�D������āA���{����č��s���ւ̑��蕨�Ƃ��āA�g�����O�̐v�ɂ�茚�z���ꂽ���̂ł���B �@�����̓��R�@�̉��G�́A�Ǘ���̕s���ɂ��S�đ������Ă��܂��܂��Ă������A�ŋ߂ɂȂ��Đ�Z�����̉��G20�����Ő���A���N5���Ɋ���邱�ƂƂȂ��Ă���B �@����A�R����p�قł��̉��G�������J����Ă���Ƃ����B�e���r�����I����Ă����ɎR����p�قɋ삯�����B �@�����͍���Ƃ͂����ĕς�����D�V�C�B�����傩��̎U�����y�����B�܂������̂ʼn��G��Ɛ肷�邱�Ƃ��ł����B���ɑ�Q���ł́A������l���O���̉��Ɉ͂܂��Ƃ����K�^�Ɍb�܂ꂽ�B
�@��Z�͌���A�[�g�Ŏg����A�N�����G��𗬂����݁A�������A�Ō�ɏ��߂ē��{��̕M���g�p���Ă��邪�A�o���オ�������̍�i�͂܂��ɓ��{�����̐^����\�����Ă����B�č��ɂ����邱�̂悤�Ȑ�Z�̊����́A���ݓ��������ߑ���p�قŊJ����Ă���u���{�G��̗h�炬�v�̉�������ɂ���B�����Ă��̉���́A�t�B���f���t�B�A�́u�������v�Ƃ����`���I�ȓ��{���z�̒��ŁA�u�V�������{�G��v�Ƃ��č��ۓI�ɍ����]�����邱�ƂɂȂ�Ǝv���B �@��Z�̌Â���i�Ƃ��ẮA1984�N�̃r���V���[�Y�ƌĂ��s�X�E�Z�ɁE��t�A�s��i�t�A�s�f�s�̋L�^�t���o�Ă����B���{�v���̏ے��I�s�s��ł���B1987�N�́s�����t�͎ߎO��ɕ������������̊G�B1989�N�́s����t�́A�����͏]���̓��{��ł��邪�E���͓c���ꑺ���A�����E���\�[�Ƃ����������I��i�B1989�N�́s���E�k�J�t�͎R�����̔N�ւ悤�ɕ`���ꂽ�s�v�c�ȍ�i�B���N�́s�l�G�E�t�t��2000�N�́s����t�̓C���p�N�g���ア�B1997�N�́s8���̋�Ɛ�t�͖n�����炵����ɏ����Ȍ���`�������̂炵���B �@�ŐV��i�́u�t�H�[�����O�J���[�Y�v�́A������낢��ȐF�ʂŕ\���������̂ł���B�I�����_�̗F�l�Ɋ��߂�ꂽ���̂��Ƃ����B�m���ɐԂ̑�͑N��ł��邪�A10��ވȏ�̑ꂪ�o�Ă���ƃA���f�B�[�E�E�H�[�z���̃}�������E�������[��ё̂悤�ł����Ƃ��Ȃ��B (2006.12a) |
| ����W�u�������p�̖��i�v�F�ޗǍ���������
|
| �@�������̋������o�āA�n������������Ƃ������ޗǍ����������ɒ����B����͖{�قɓW������Ă��鐔�������������ĉ�����B���C���e�[�}�́u��a�̕������v�ł���B �@�������O�ɂ͖��T���ɉ����Ԃ��������Ԃɏ���ċ��s��ޗǂ̕����ɉ�ɍs���Ă������A�킽���̏ꍇ�����̓R���J���ł���B���m���p�A���{���p�Ǝ���Ɏ����̋������L�����Ă������A�m����������ƂƂ��ɖʔ������[�܂��Ă��Ă���B�����̏ꍇ���m�������������₵�Ă��������B �@�{�����e�B�A�̕����t���Y���Ă����������̂ŁA�y������b���Ȃ�������邱�Ƃ��ł����B���܂��R�ς����Ď��E�����Ȃ��̂ŁA�����ł͍���̖ڋʓW���𒆐S�ɋL�������������B
�@�@�����̋����l�V�����̂����́s�����V�����t�̓W�����s���Ă����B����̂��̂ŁA����Ȍ�̂��̂Ƃ����炩�ɈႤ�B�����͂Ȃɂ��Ȃ���������Ɨ����Ă���B�����Ԃ�ȑf�ł���B���̑����V�͈����S�݂��Ă��邪�A���̕����ł̓C�^�Y�������Ɏ�������グ���V�S�ł���B �@���̂悤�ɕS�ϊω��Ɠ������̍����C�Ȃ�����W�ɓW������Ă���Ƃ���ɓޗǍ��������ق̐���������B �@�{�����e�B�A�͎l�V���̐��������n�߂��B�}�[�W�����̓��쐼�k�i�g���E�i���E�V���[�E�y�[�j�ɂ��킹�Ď����V�E�����V�E�L�ړV�E�����V�i���E�����E�����E�����n���������j�A���o�̗E�ԁE���E���[�ɑ�������A�����V�͒P�Ƃł͔�����V�ł���Ƃ��������Ƃł���B���E���E�L�E���i���E�����E�����E�����n���������j�͒m���Ă������ق��ĕ����Ă����B
�@�u���ڂ̈�i�v�R�[�i�|�ł́A�ؑ��́s���������V�����t���o�Ă����B����ّ͊��̏d���ŕ��������ɓ�����`�������݂͓����ɂ��銕�������V�����̖͍��ł���B�����11���I�̍ʐF���łȂ��Ȃ��̏o���h���ł���B�����͑傫�����Ă����������Ă��ٕ��������邪�A���̑�����164 cm�ł��邩��l�ԕ��݂̑傫���Őe���݂₷���B �@�u���������V�v�͐���̊��덑�i���݂̓f�D�ԃg���t�@���Ƃ��f�׃`�x�b�g�Ƃ�������j�ɏo�������Ƃ����A�������̂��߂ɏ��Ɉ��u�������̂ł���B�ʌ`�̔�����V�͎C��ł��邪�A���������V�͒n�V����������x���Ă���̂ł����ɕ�����B�������������ق́u�����W�v�ɂ����������哰�̂��̂��o�i����Ă����B �@���̕����́A�P���������������Ԃ�A����ȊO���̂悤�ȕ����܂Ƃ��A�r�ɂ͊C�V�Ď�A���ɂ�������t���Ă���B �R�D���̑� �@�������ׂ̋��������������̒E�����������R�̂ƍs�ꍿ�������Ă����B�������́u����فv���������邩�炾�낤���B �@�܂����w�������W�߂��R�[�i�[������A�������B�Ƃ��ɓ������́s�ؑ����w�t�͑f���炵���F�ʂ��c���Ă����B (2006.12a) |
|
|
| �@�������̂�����Ɏw�肳��Ă���B���͑����A�G���Ă݂��15���I�̎��̐������`����Ă���B�O��Ԃ����������ƂȂ��Ă��芦�����������Ă���B���̂悤�Ȋ��Œ������Ă����镧�����͊F�͋����B �@�P�D��t�@�������@�i��������A1415�N�j�F�����B�@���X�Ƃ����Ќ����������������ł���B���Ƃ���726�N�ɐ����V�c�������V�c�̕a�C����������č��ꂽ�����̍ċ����B �@�Q�D�����E������F�����@�i���P����A7���I���j�F�@�����B����قɂ��镧���ƂƂ���1187�N�A�R�c�����狻�����̑m���D���Ă������́B �@�R�D�����F�����i���q���㏉���j�F�@��ؑ��B�ӂ��悩�Ȋۊ�ŁA�̊i���ǂ��A��X�������`����Ă���B�~���̉��Ɏ��q�B����́u����������W�v�ł݂��B �@�S�D�ۖ����m�����i���q����A1196�N�A��c�j�F�@��ؑ��B�ʎ��I�Ȓ����Ƃ��čL���m���Ă���B�����Ђ��߁A��������ɂ݂��錃�����e�e�⑉�������͕̂����F�ƑΏƓI�ł���B�l�p���̉��Ɏ��q�B������u����������W�v�ł݂��B �@�T�D�\��_�����i���q���㏉���j�F�@��ؑ��B�_�C�i�~�b�N�ȓ����̕\�����f���炵���B������̑�������ɂ͏\��x�̕W������Ă��邪�A�Â��̂ŒP�ዾ�Ō��Ă����ʂł��Ȃ��B�啔���́u����������W�v�ł݂Ă���͂������A�ǂ�������̂����o���Ă��Ȃ��B �@�U�D�l�V�������i�������㏉���j�F�@��ؑ��A�{��̕\���������ł���B (2006.12a) |
|
|
| �@2004�N�́u����������W�v�Ŋς邱�Ƃ��o���Ȃ������z�g�P�T�}�����Ɍ�������肾�������A�ĉ���ʂ����������̑O��������肪���������B����Ɏw�肳��Ă��镧���Ɍ����ă������Ă����B�����N���������f�[�^�x�[�X�ɒ��点�Ă����������B �@�P�D�����@�i���P����A685�N�j�F�@���Ƃ͖ŖS�����h�䎁��Ǖ炷��̎R�c���̖{���ł�������̏�Z��t�@�����B1187�N�ɋ������̑m�ɒD���ē������̖{���ƂȂ����B1411�N�̉ЂŊ��S�Ɏ���ꂽ�Ƃ���Ă������A�P�X�R�V�N�Ɍ��݂̖{���̑���̒����瓪���������������ꂽ�B �@�Q�D���C���@�i�V������A�V�R�S�N�j�F�@�킪���ł����Ƃ��l�C�̂��镧���̂ЂƂB�O��͉������ڂɂ����������Y��Ă���B�C�w���s�̎���������Ȃ��B �߉ނ̐������삷�锪���O�̈�l�����A�͈̂��S�������Ƃ̂��ƁB ���͎O�ʘZ�]�A�㔼�g�͗��ł���B��͐��ʂ͔����Ђ��߂��[���ȕ\��ł��邪�A���E�̖ʂ͂������Ė��\��ȏ��N�̂悤�Ȋ���B�]���ȋؓ����������Ƃ���A�L���L�т��S�{�̘r�ƍ��������Q�{�̘r�͂��̑��ɑf���炵����Ԑ���^���Ă���B �u�͂�ڂāv�̂悤�Ȋ������Ōy�����߉Ђ̍ۂɂ������o����A���������̂ł��낤�B���̓����������ٌ`���ޘO�����܂ނ��̑��������O���\���q�̂Ȃ����Z�����������ł���B �@�R�D���\��_���i��������j�F�@�f���炵���o���h���ŁA���ꂼ��̓������ǂ��\������Ă���B�����̂�����̂̓g�N�Ɉ�ۓI�B���{�ɂ����̂悤�ɐ��E�ɒʂ���Z�@�����y���Ă����Ƃ͒m��Ȃ������B �@�S�D�@���Z�c�i���q����A1189�N�A�N�c�j�F�@�ꕔ�́u����������W�v�ł��ڂɂ������Ă���B�ƂĂ��ʎ��I�Ȓ����ł��邱�Ƃ��Ċm�F�����B�@ �@�T�D�����͎m�i���q����j�F�@�����J�������`�ƌ�������`�B���̈�ۓI�ȍ�i�͓����̓W����łٍ͈ʂ�����Ă������A�ޗǂł͕��l�̒��ɂ���Ȃ�Ɉ��Z���Ă����B �@�U�D�V���S�E�����S�i���q����A1215�N�A�N�فj�F�@�����J���A�����ɓ��Ă�S���ԋS�u�V���S�v�ƌ����w�̎��̌���œ��Ăɏ悹��S�u�����S�t�ɂ��ĉ�ł����B�܂�������������[�����X�ȍ�i�B �@�V�D���ω��i���q����j�F�@����ق̒����ɓ��X�ƈ��u����Ă���B�V��܂œ͂������Ȕw�̍����B����ł͓����̓W����Ɏ����Ă���͕̂s�\�ł���B�����̑��l���͋��ٓI�B (2006.12a) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@ �u���O�ɏ���������ŋv���U��ɓޗǂɗ����B���̌������p�ق͂܂������F�C�̂Ȃ��n�R�B�ł�����̒����͔��Q�B�����ƈ���̎t��W�ł���B�O���ƂقƂ�Ǒ����ւ̌���ŏI���Ɋ��荞�B
�@�e�[�}�ʂɉ����ƈ��Ⴊ���ׂ�ꎩ�R�Ɨ��҂��r����悤�Ɏd�g�܂�Ă���B���̌v��ɏ���Ċ��z���������Ƃɂ���B�@
�@���Ă�������ĊςĂ���ƁA�����͓w�͂̐l�ł���A�����Ĉ���͊����̐l�ł���Ƃ������Ƃ�������B�ÂƓ��Ƃ����Ⴂ�ɖڂ�������l������B���̂悤�ɂ��ꂼ��̌��ɈႢ�����邱�Ƃ͊m���ł��邪�A���̓�l�̉�Ƃɂ͂����̑�������邾���̐������̋��ʓ_�E�ގ��_�����邱�Ƃ�����̓W����͋����Ă��ꂽ�B�������g�A���܂œ�l�̑���_�ɂ���ڂ������Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����Ă���B �@�l���E�Ԓ��E�R���̂�����ɂ����Ă����͂���߂Ď��Ă���B��l�̎q���ɑ��鈤��[���፷�������邾���ŁA���̓�l�̎t��Ƃ��Ă̘A������ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B�����́s�g�����T�}�t���ς�ƁA�ނ�����̕����Ȃ��u�V�ѐS�v�������Ă������Ƃ�������B���̂悤�Ȏ��R�ȕ`�������o�������ۂ��́A��Ǝ��g�̌��ɂ��Ƃ��������A���̒u���ꂽ���ɂ��̂ł͂Ȃ��낤���B (2006.12a) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
�U�D���a��O���̔��p
�W�D1950-60�N��̔��p (2006.12a) |
| �h�炮�ߑ�[���{���m��̂͂��܂ɁF���������ߑ���p��
|
||||||
| �@���{��Ɨm��Ƃ�����̃W�������ɋ�ʂ��ꂽ�̂�1907�N�̕��W�ł���B���̓W����͓��{��Ɨm��̕����Ƃ���100�N�ȏ㑱�������̎������������Ă݂悤�Ƃ�����̂ł���B���̊ϓ_����ߑ�G��j���l����ƁA��i�A��Ƃ̑��̎����Ɛ��x�̎����̕s��v�Ƃ����������N���[�Y�A�b�v�����B �@���̓W������ςĂ����ƁA���ۂɂ͂��̓�̃W�������͏��߂͂���قǂ͂����肵�����̂ł͂Ȃ��A���Ȃ�l�דI�Ȃ��̂��������Ƃ��ǂ�������B �@�����Ƃ͗m��Ƃ�����{��Ƃւ̕ϐg�𐋂��Ă���B���̋t������B�����Ƃ͈�̉�̒��ɑ�a�G�E���E�����G�ȂǓ`���I�ȓ��{��̗v�f�Ɨm��̗v�f�����݂��������`���Ă���B��̃R���Z�v�g�݂̂Ȃ炸�A������|�����Ɗz���Ƃ����Č`���A����ɂ͊G��Ȃǂ̍ޗ������݂��Ă��邱�Ƃ�����B �@���̂悤�ȓ��{��Ɨm��̒��Ԃɑ������i���ς�ƁA���҂̏Z�ݕ����Ɋ��炳��Ă��܂��Ă������ꌻ��l�́A�Ȃɂ��s����Ƃ������ׂ��s���Ȋ��o�ɂƂ����B �@���́@���F�R�E�����R��A���{��Ɨm��̎n�܂�F�@���F�R�́s�m�����S�t�����m�痿�̋����F�ʂɂ���čʂ��A�����R��́s��i�C���}�j�t���]�ˊG��Ɏ����\�}�������悤�ɁA���{��Ɨm��͂��́u�͂��܁v�Ɉʒu�����i����͂��܂����B�����R��́s�ʐ����i�u�ԘM�ʁj�t�͖k�֖���̍Č��̂悤�ł���B �@���́@���{��̐[�w�A���{��Ɨm��̍����F�@��Ƃ����͓��{��Ɨm��́u�͂��܁v�Ŏ�T��Ŏ����I�Ȑ�����s���A���s���낵���Ղ����ĂƂ��B�͓�ōւ́s�͒|�و����w�Y����材��m���x�p���X����\�|��̏�t�A�{�X�g�����p�ق��痈���r�Q���[�E�R���N�V�����̏��щi��̎O��i�⋴�{��M�́s�ٓV�t�͌�����������B�d��哿�́s�a�m���t�V�}�t�̓��@�C�I�����Ǝڔ��̍��t�A���{�I���ʉ��\�����s���G�����t���ʔ����B�@�쑺���Y�́s�e�z�t���ǂ������B
�@��O�́@���{�G��̒T���@���{��Ɨm��̍���F�@���{��Ɨm��Ƃ����T�O���������Ă��Ȃ��A���{��Ƃ͓��{��̊v�V���A�m��Ƃ͗m��̓��{�������߂�X��������A���{��Ɨm��̋�ʂ����u���{�G��v��ڎw���Ă����Ƃ�������B ��䒉�̓��{��s���i�@�t�t�A�|�����P�́s���F�j�X�̌��t�A�A���c���P�́s�Ԃ��߂𒅂��鏗�t�A���R��ς́s���q�t�A�H�c�t���̏H�ؗ��t�͈�ۓI�ȉ悾�����B
�@��́@�m��̒��̓��{��F�@�吳���̗m��Ƃ́A����łœ��{�̕��y�ɍ��������G��\�����Ȃ킿�u���{�I���G�v��͍������B�A���╽�ʓI�ȉ�ʍ\���A�G��̂��̂̎����A�����Ȃǂ̌`���ɊS����ꂽ�B ���c�k�́s�^�s�X���[�̗��w�t�͓����F�̗��w�ƔL�ƉԂ̃A���T���u���ŁA���{��ׂ̍��֊s�����̗p���Ă���B���o��d�́s���|�~�����t�͔ނ̍�i�Ƃ͂قƂ�ǐM�����Ȃ������`���̗͍�B�J�����X�g�ƌĂ��~�����O�Y�́s�k���H��t�̋�͖��ʂ����A�{�a�ɂ͊�G����g���Ă���B �@��Z�́@�h�炮�ߑ��Ƃ����@���{��Ɨm��̂͂��܂��F
���{����m����̂�������Ƃ��Љ�Ă���B �ݓS�ܘY�A�ݓc�����A�X�c�P�F�A������佁A�ߓ��_��H�A�{�c�����Y�A��[���q�A�f�e���A�F�J����9�l�ł���B������佂́s��������t�A�{�c�����Y�́s�Z�q�t�E�s�V���t�A��[���q�́s�����t�A�F�J���́s���e�L�t�E�s�C�̐}�t���Ƃ��ɗǂ������B
(2006.12a) |
|
|
|||
|
�@���{�v��̓����Ɛ�������̉������s�X�t�����̔��p�ق��\����B���̓��O�Ȑ̒��ɐ��ޕs�����B����͎���̓��e�������{�̐S�ە��i�B���{�́s�j�R���C���t�A�s�^�͕��i�t�A�����Đ�M�́s�����t�������x�������B �@��c�p�v�́s�s��t�B���̔��p�ق�L���ɂ��Ă����i�ł���B����̓A�����J�Ɠ��{�̋��Ԃɗ�������c�̐S�ۓs���B �@���������̑��ɂ��D��i���ڔ������B�L����K�i�̕ǖʂɂ܂œW������Ă���A�������p�ق��͂��������B �@��������̃p�X�e���s�u���[�^�[�o���t�͑f���炵�����������B�֍�����́s�Õ��E�ԁt�͔ނ����߂Ă�܂Ȃ��������@�[�~���I���̊G��d�Ȃ�悤�ɓh�肱�߂��Ă���B�O�ݐߎq�́s�ԁt�̔��G������l�ł���B�ޏ��̉�̖T�ɂ́A�D���Y�̎���ޏ����͂��������ɗ������N���̐���\��̉悪�|�����Ă���B�����o�V�́s��v���t�͊O��������]�R��ƂƂ��Ċ��������̒ɍ��̍�i�B�V���j���p�قł��Љ��Ă������A�����o�V�W�����ł͂���1�_�������َ��̑��݂������B
�@���蓡���̎O�j�ł��铇���Ꮥ�́s�����[�x�b�N�ɂāt�͊��F�ɕ����߂�ꂽ���i�B�������Y�̔����ɉf��W���s�e�t�́A�����ɑ傫�ȑ��̂��镔���̋��ɂ����Ă��������A���̑�����͍g�t�A�����Ă��̌������ɂ͋ː��̊X�����]����A�f���炵�����͋C���������o���Ă����B���c�v�́s���ƒ��t�A�x���E�V���[���́s�_�v�t�A�s�J�\�́s�C�V�Ɛ������t���悩�����B �@��70����W�́u�s�s�Ɛ����[�������ւ̂܂Ȃ����v�ł���B���߂ɂ����ƌ������ɂ͎G���ȉ悪����ł��邾���̊��Ɗ��������A�M�������[�����[�g�[�N���ė������[�܂����B���W�͏����������Ȃ���4�͂ɕ����Ă������B
�@��2�͂́u1970�]90�N��̑�ʐ��Y�E��ʏ���̂킪���̓s��v�B���c�ߕv�́s���b�V���A���[2�t�͏a�J�w�ł킽����������Ă������i�B �@��3�͂́u�s�s�̒��̉�Ɓv�B���䋂�́s�t�F�X�e�B�o���E�h�E�g�E�L���E�t�͊e���̌��t���č��ۓI�ɒʂ���}�[�N�̏W���B���������́s����U�t��7�����炢�̃v���L�V�K���X�ɃV���N�X�N���[���Œ������ꂽ����̐l�������B�f��̃V�[������Ƃ������̂Ƃ̂��ƁB �@�Ō�́u�h�~�g���[�E�~�g���q���̊X�Ɛ����v�́@���\�r�G�g�A�M�̉��₩�ȓ��퐶�����ʂ����ʼn�B�����Ɛ����͕ʂ̑��݂ł���B �@���_�Ƃ��Ă����A���{�v����c�p�v�̐S�ۓs���̌n�������̊��W�ŏЉ��Ă����̂ł���B (2006.11a) |
| ������{�於��W�F�����q�s�����p��
|
||||
| �@�����q�s�̎s��90���N�L�O�Ƃ��ĊJ����Ă��錻����{��d���\�����Ƃ����̍�i�W�B���ׂ�20���I�Ɋ�����Ƃ̖k�V���p�ُ�����i�B���ɓ���ƎR���ؗk�́s���ρt���}���Ă����B�ǂ����Ŋς��Ƃ����f�W�����B�����ʼnؗk�́s�`�t�Ɓs�H���t�B���̓�̍��L�́A�H�c�t���́s�����L�t�̒|�����P�́s�ǔL�t���Ő��F�̖ڂ����˔����Ă���B�w�k�V���p�ُ������{�於�i�W�x�i�����o�Łj�̕\���͂��́s�`�t�B�s�H���t�ł͒��H���̂���`�̗t�̂��炵���݂��▭�B
�@���̕����͓��R�@�̕����B�������Ƃ���ɂ́s�̃n�C�f���x���O�t�B��̂悤�ȗɉ��ޏ�i�͎��ɑf���炵���B�A���g�E�n�C�f���x���N�̉S�u���������͂��ƁA�l�b�J�[�̐�̂Ȃ������A�݂ɗ��܂����䂪�N�ɁA���܂������̏t�́A���Ɨ킵���ԏ���B���������܂��䂪�ƂɁA�����ꋎ��܂���������A���̂ю���Ⴋ���́A�n�C�f���x���N�̊w�т�́A�K�������̑z���o���v���v���o������I�ȍ�i�B�@�͎Ⴂ���x��������w�ɗ��w���Ă���B���}���`�b�N�ȑz���o�ł��������̂��낤���B�����̐^�ɒu���Ă���֎q�ɍ����ās���e�t�E�s���t�E�s����t�Ȃǂ̖��i�Ɉ͂܂ꂽ�B���ꂼ�ᕟ�B
�@���R�����́s�V��̍����t�̐͐�i�B��̐��R�̗Ő��ƂȂ�A�[�ŗ��ƂȂ�A�ĂъC�̐ƂȂ�B�܂�Ŏ��R�̉c�݁B�Ő�����߂�Ԃ̃A�N�Z���g���s���B�������R�ł̐�Ԃ͒J�̐V��̔���w�i�ɂ��Ă��邩��ڂɔ�э���ł���̂ł���B����A���R���́s�ԕx�m�t�ł́A�^���ԂȎR�≩�F�����ɂ�����ꂽ�u����ʂ��点�肠�����Ă���B���c���v�́s��P�t�͒����ɋP���֒�R���ܐF���Ɏʂ��Ă���i�F�ł��낤���B�@�����F�ɐ��܂�R���͉��Ƃ������Ȃ��B�s���J�̌t�͍g�t�̉f����X�[�b�g���鐅���B���c���v�͂܂������u�g�t�̉�Ɓv�B
�@�쑺�`�Ƃ́s��F�t�͌Ñ�M���V����ՁA�s�����t�̓S�V�b�N����B����������z�I�ȃ��[���b�p���i�B�@���I�ȍ��݂ɒB���Ă���B�p���ɂ��A�g���G������Ƃ����B���ꂼ���ۓI���{��B���邢�͓��{��Ƃ������t�͂��łɒ������Ă���Ƃ����ׂ��Ȃ̂��낤�B�@���R�́s�ł̎��t��H�ׂ郊�X�̖ѕ��݁A�����ās��x�t�����ƒ|�Ƃ̃��A���e�B�[�ɂ͋������ꂽ�B��{�K�d�́s���t�͐V�����ɏ���Ă���T�P�����A���̃E���R����i�B�ƂĂ����t�ɂ͕\���Ȃ��B�V�����̕������菑���̂悤�Ɍ�����B�������Q����̂݁B (2006.11a) |
|
|
|
�R�D�����I�G���i1960��㔼�`1970�N��O���j �S�D�S�ۓI�G���i1970�N��㔼�ȍ~�j �}�^���W�����ɒu���Ă������̂Ŏ����Ɣ�ׂĂ݂����摜�����邷���ē�����ɂ͌����Ȃ��B��̐������s�\���B�������܊p���H�����̂�����ƈꉞ��t�ł����Ă݂���A���ŁE�ĔłƂ��ɔ����Ƃ̂��Ƃ������B�~���[�W�A���E�V���b�v�͂��̎�t�����B �R���s���[�^���ŎR�{�u�l�̃r�f�I�������B�W����i���ǂ�ǂ�o�Ă��Ċy���߂��B��������������Ă��Ē����ɂ����B���Ƃ��Ȃ�Ȃ����̂��B ���X�g�����͋Ă���̂ɂЂǂ��҂����ꂽ�B��ۂ̈����j���E�F�C�^�[3�l���E���E���A�V�F�t��1�l����������̂悤���B���͂悩���������炢�炵���B (2006.11a) |
| �@ |
| UKIYO-E(�����ƔŌ��j�F�`���y������
|
||||||||||||||||||||
| �@�`�搭60���N�L�O���ƂƂ��ĊJ�Â���Ă��镂���G�W�B�`����ɂ͑����̖���������A�]�ˎ���ȍ~�̂��̏�i�������G�Ƃ��Ďc���Ă���B�܂����݂̕l�����Ƒ��̂�����ɂ͓��{���Ɏ����ŔŌ��������A���݂̌��t�ł����Ȃ�A���̒n��͏�M��n�ƂȂ��Ă��������ł���B �@�S����250�_���̑�W������A����قǍL���ꏊ�ł͂Ȃ��̂ŁA�O���E����ɕ�����Ă���ق��ɁA�T���E�U���E�V���ɂ�������Ă���B�S�̂����悤�Ƃ����4���^�Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�Ȃɂ������ł���B����������؍����͂܂������Ȃ��B���炭�O�c�}����4�K�ɂ����`���y�������ʂ�������l������̂ł͂Ȃ����B ��1�́@�����F�@���z�E�G�E�R�E�ԍ�E�����E�Ճm��E�ԉH�E���㎛�E�Ő_���E�C�ݐ��E�ʼnY�E�V���E���ցE��x���Ƃ���Ίm���ɖ������낢�ł���B �@�ԍ��ł́A�}�����Q�́s�I�̍���~�J�t�E�E�E�����̉J�i�F�̒��ɎP����������l�̐l���������W�����F����Ă���B��l�͐̒����̏����A������l�͂�⍘�������߂��V�l���B���݂̓z�e���E�j���[�I�[�^�j�̋߂������A���m�ȏꏊ�͕�����Ȃ��B �@���̐�L�d�́s�ԍ�˔��J���[�����t�E�E�E�ߌi�͐���̂ɒ��F����Ă��邪�A���i�͔����Ō��z�I�B�����̎R�̎ΐ��A�����̉J�Ȃǐ��̃R���g���X�g���I�݂ł���B �@�O��̐�L���́s�]�˖����S�l�����@�Ԃ����X��t�E�E�E�ؗ�Ȓ����̏������A���Ȃ₩�Ȏw�ŋՂ�e���Ă���B�u���[�̑т������ɂ��f���炵���A�R�}�G�̂Ȃ��ɂ͕X��_�Ђ̒����Ɖ������`�����܂�Ă���B
�@�����ł́A�̐�L�d�́s�����]�˕S�i�@�ň����R�t�E�E�E�u������V����̌����v���傫�Ȃ�������������Ĉ����_�ЂA���Ă����Ƃ���B���ƖY��Ȃ����j�[�N�ȊG�B �@�O��L���́s���s�����R�̕��i�t�E�E�E�������F�ʂ�3�����B�ߌi�ɂ͒n�������f���炵���͗l�̒��������������̏�����4�l�A���i�͔������̕����Ԑ������p�B���̉��11��17�]23����1�T�Ԃ����ς��Ȃ��I �@�̐�L�F�N�́s���ѕ����e�k�@�Ȗؕ���Y�t�E�E�E�R�~�b�N�B
�@�ԉH�ł́A�̐�t���́s�ԉH���̕��i�t�E�E�E�̔��F�̗ǂ�3�����B�Ղ�O�������������Ԋ@���ߌi�ɁA�L�n���~��㎛�d�������i�Ɍ�����B �@���㎛�ł́A���L���́s�������Ŕ��i�@���㎛�ӏ��t�E�E�E�Ԗ͗l�̒������������̏㔼�g�B����������ꂽ���B���`�̃R�}�G�ɂ͗[�Ŕ��鑝�㎛�B �@�Ő_���ł́A�̐썑��́s���q���P���F���t�E�E�E�ł̐_���{�ɂ��S�x�Q������鏗���B���Q��̂��тɎ�Ɏ������m�������Ă����炵���B���ɂ܂��e�����J���C�C�B����̓W����̃`���V�͂��̊G�B �@�C�ݐ��ł́A���̐썑�j�́s���������@���{�����֔V���i�@�q�������ѓZ�������t�E�E�E���S�l�Ƃ����q�������h���̕����ŕ���ł���B�P�ዾ�̂Ȃ��Ɏq�������̖��邢�\������Ă���B
�@�ʼnY�ł́A�L�d�́s�����]�˕S�i�@�ł���V���i�t�E�s���@�������@�ʼnY�t�E�E�E�O�҂͉��ߊ��̐S�n�悢����A��҂͛�̐Ԃ������B �@�V���ł́A�O��L���́s�]�˖����S�l�����@�V�͂��t�E�E�ڂ߂��P�ɁA�����ʁA�����Č����炩�����z�����ɂ��킦�鉐�������p�B���v�̕`�����R�}�G�̐V�����ʔ����B �@�����ł́A�L�d�́s�]�˖����l�G�@�����̌i�t�E�E�E�O��ł͒������������A�H��ɂ͗��̉��Ă����B�ɒ[�ȉ��ߖ@�Ŋ��̈Ⴂ����������Ă���B �@�k�։p��́s�]�˖������l���t�E�E�E���������ɂȂ��Ă��郉�u���^�[�̈ꖇ��ǂމԊ@�B����͔��l�I�͂����������猩���鑫�w�̋Ȃ��肪�C�ɂ�����B�R�}�G�̂Ȃ��ɂ͕x�m�R�B �@
�@�L�d�́s�s�֔V�}�t�E�E�E�����̍s��B�Ă��������S���Ȃǎ��ۂɂ͂��肦�Ȃ��z���̏�i�B�}���K�̂悤���B �@��x���ł́A�y������́s����x���t�E�E�E���a����̉�ƁB��i�̂Ȃ��̌��̕\�����▭�ł���B �@���F�́s�����`�m�����V���@�����{�]�V�}�t�E�E�E�n�V�S���˂��ċg�Ǔ@�ɓ�������Ƃ���B�����̐�A�����A�����̊�̌Q��ȂǍׂ����_���`�����܂�Ă���B ��2�́@�Ō��F�@ �@�Ő_���n��̑�\�I�ȔŌ��s�a�s���q�t�̔Ŗ{�Ƃ��ẮA����t���́s�G�{�h�Ǝ�t�A����́s�����Z������t�A���F�́s�����Y�w偊����t���ǂ������B �@���̑��̔Ō��̍�i�Ƃ��ẮA�s�ێR�r���t�o�ł̏���t�͂̒��G�s���㒆�������@�H���S�o[�]��N��L]�t�͖{�W�����̌���B�����͂����A�������������A�����߂��ʂ����Ȃ���Ȃɂ��l���Ă���j�B�����������F�����ŁA���Ƃ������Ȃ��B �@���쉮�약�o�ł̌k�։p��́s�������l�\��ӌ��@�Ő_���������s�㌎�t�A�ዷ���^�s�o�ŁE���F��́s��\�l�F���q�Ӂt�A�L�c�����E�q���E���F�́s栘_�������֑����@���t���ǂ������B
��3�́@�G�t�F�@ �@�i�n�]���́s���l�}�t�A�̐�L���́s���ҕ���V�p�G�@�����炢��t�A�쐣�b���́s���㎛�̐�t�͂�������D�i�ł������B
�i�ǁ@�L�j�@��V�����n�܂��Ă���̂ł�����x�ςɂ������B���x�̌����͉̐썑��́s�G�Z�풉�b���t�B���F�̗ǂ�11�i�̑����B�����̏����𒉐b���̓o��l���Ɍ����Ă��V���[�Y�ŁA�w�i�ɂ͊e�i�̖���ʂ��`����Ă���B�������蒭�߂Ă����B �@���̑��ɁA���ʓW���̉̐썑���́s�V�ň����ɕ��G�@�y���C�����l�����t�͖ʔ��������B���ߖ@���g�������[�h�X���̋��l���B�҂̊Ԃ�傫�ȑD���ʂ�B�E��ɂ͔��̉��̏o��ق��f���A�E���ɋ|��S���A�E��ɞ��_�̂悤�Ȗ�������Ă���B �@�쐣�b���Ȃǂ̐V�ʼn�ɂ��ǂ����̂����������B���̓W����̃|�X�^�[���ł����������B���ꗿ�������Ȃ̂����璴���ӁI (2006.11a) |
| ���{�W�i���p�ك{�����e�B�A���I�ԃR���N�V�����W�j�F��t�s���p��
|
| �@��t�s���p�ق�32�l�̃{�����e�B�A����悵���W����B �u���{�W�v�Ɨ�����Ă���B�W���i�I��A�|�X�^�[�}�č쐬�A�W�����C�A�E�g�Ȃǂ��ׂĂ��{�����e�B�A���S�Ői�߂����̂Ƃ����B ��7000�_�̏����i�̒����瓊�[�őI�ꂽ57�_���W������Ă���B �@ ������p�E�ߐ��ߑ�ʼn�E�ߐ��ߑ�G��̒P���ȏ͗��āB���������Ԃ����͗��Ă̑����ŋ߂̓W����̒��ł͂������ĐV�N��������B
�@���ɂ����Ă͍]�˓��������قŊJ�Ò��́u�]�˂̗U�f�\�r�Q���[�R���N�V�����v�Ɉ������Ƃ�Ȃ���������Ȃ��B
�@ �@�{�����e�B�A�̑I�g�b�v�T�́A�@
�쑽��̖��u�[�����l�}�v�A �A�����u���u���F�߉ޏ\���q�v�A�B�~�R�����u�H���ዬ�}�v�A�C�L�ؐ����u�O���v�A �D�l���z�O�u�P�X��1�̂������ځv�Ƃ̌��ʂ����o���ɕ\�����Ă���̂͂ǂ����Ǝv���B���̉��Ɋϋq�̓��[�����u���Ă��邪�A�S���I�ȉe�����������Ă��܂��B�����܂ł��ϋq����ŁA�{�����e�B�A�͏]�łȂ���Ύ�q�t�]�ł���B (2006.11a) |
|
|
|
�@�x���ł����邵�A������x����ł��邱�Ƃ��o�債�Ă����̂����A�ӊO�ƋĂ���B�S�̂�4����1�قnj����Ƃ���ŁA�������Ƃ�Ȃ��炱����Ɍ����Ă���j��������B�u���Â₳���v�������B�����ňӊO�Ȕ����ɂ��Ă̈ӌ������������B��͂苻���������Ƃ���Ɍ����Ă����炵���B �@ �]�ˎ���̕��l��Ɓu�Y��ʓ��v�i1745�`1820�j�́A�h�C�c�̌��z�ƃu���[�m�E�^�E�g�ɂ���ăS�b�z�ɔ䂹���A�u�ނ͓��{���p�̋�Ɍ�䊂�I���a���̂��Ƃ��A�Ǝ��̋O������B�v�ƌ�����Ƃ̂��Ƃł���B �ނ͉��R�̕��m�ł��������A50�ŒE�ˏo�z���A�S�����������A���s�Ŏ��ƋՂ������A�ق됌���̒��ő������t�̂悤�ɎR�����`�����B
�@���ɓ������Ƃ���ɂ���͔̂~�����O�Y�����́s�ΎR���Ր}�t�B �R���ނ����悾���A�Ƃ���ǂ���ɔ������̂悤�Ȃ��̂�������Ă���B�L���v�V�����ɂ��Ƃ���́u�A�z�v�z�Ɋ�Â��j���C���[�W�v�Ƃ̂��ƁI�{�����ȂƎv���ĊςĂ����Ǝ����悤�ȃC���[�W�������i�����\����B�啪��̂ق������A�s�R���LjՐ}�t�̃L���v�V�����ɂ��Ռo�̒j���̉A�z�Ƃ̊W��������Ă���B���������ڂŌ��Ă݂�ƁA������Ƃ��������C�ɂ��Ȃ��Ă���B�s�H�ъԓK�}�t��1�̓��������Ȃǂ͏����C���[�W�H���������Ώd�v�������́s�ۋ]�����E������ΐ}�t�͂��̂悤�ȃC���[�W�̏W���I��������R���̑��Ɉ͂܂�Ă���ƁA����炪�j���̏ے��Ɍ����Ă���B�Ƃ����킯�ł�������ʓ��i���邢�͐�t�s���p�فj�ɂ���Ă��܂����B �@�Ђ���Ƃ���ƃL���v�V����������������₷�����͂ƂȂ��Ă����̂ł��낤���B����o�ʼn�̎G���uUP�v�̍ŋߍ��ɐ�t�s���p�ْ��E���ђ����́u���y�Ǝ����G�ɂ����R����ƁA�Y��ʓ���Ƃ������͂��ڂ��Ă������A����ɂ��Ɓu�V���̉B�َv�z�ɓ��ۂ��A�A�z�܍s�̎��R�̓N���ɏ]���Ď��������B���������ʓ��̐��_���y�͏I�n��т��ĕς�邱�Ƃ��Ȃ������v�ƂȂ��Ă���B �@���ꎩ�̂��������ĕ��Ղȕ��͂Ƃ͂����Ȃ����A��V���̉B�َv�z�ɓ��ہv�Ƃ͐������當�l�����ɉB�ق����Y��ʓ����������g��厩�R�̒��̏����Ȑl�ԂƂ��ĕ`�����Ƃ������Ƃ��낤�B����Ƃ��̌�́u�A�z�܍s�̎��R�̓N���v�Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��낤���B�u�u�A�z�܍s���v�Ƃ́u�A�z���v�Ɓu�܍s���v�����킳�������̂ł��邪�A�L���v�V�����̕\���͂����܂Łu�A�z���v�ɗ��������̂ł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ��̂��B
�@�s���ѐ��Ɛ}�E�t�R�J�Ӑ}�t�͛�����18���I�㔼����19���I�ɂ����Ă̕��l���Ƃ����A�c�\���|�c2�_�A�Y��ʓ�2�_�A���c���]�A�������A�r���A���R�z�A�X���ցA�����t�J�̍�i��������̂ł���B���̎����̑�\�I�����l�̂��낢���݁B �@�ʓ��̍���������Ղ����{���W������Ă����B���ƊL���G�̃R���g���X�g���������B�ނ͋Ղ̉��t���Ȃ����łȂ����ۂɐ��삵�Ă����̂ł���B���q�u�t�Ձv�̕`�����Ղ�e���ʓ��̊G���o�Ă������A�ƂĂ��G���K���g�ȕ����l�ł���B���̕��e�͓��{�̃S�b�z�Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��B���̂悤�ɕ��m���̂Ď��R���Y�p�ɐ����邱�Ƃ̂ł����]�ˎ���͂����߂��ǂ����ゾ�����̂��낤�B (2006.11a) �i�ǁ@�L�j�@2006�D11.19�̐V���j���p�٢�Y��ʓ��v�������B�Ղ̐��Ƃ̘b�͗ǂ������������A���R�������p�ق̎�������̘b�ɂ͂������肵���B�V���̉B�َv�z�ɂ��Ă͂�������b���ꂽ���A�A�z���Ɋւ��Ă͖��̃C���[�W���u�����������n�v�ƕ\�����ꂽ�����������B |
|
|
||||
| �@�c���ꑺ��1908�N - �Ȗ،����s��S�Ȗؒ��i���E�Ȗ؎s�j�ɐ��܂ꂽ�B �ނ̌̋��̓Ȗ؎s�Łu�s��70���N�L�O�@�H�̓��ʊ��W�F�@�c���ꑺ�̐��E�v���J����Ă���B�Ó�V�h���C���E���ѐ������p���œȖؓ����B���𗘗p�������j�[�N�Ȕ��p�قł���B�����������ߑ���p�������𗘗p�������p�ق��������A�Ԃ�Ă��܂����B �o�W��i�́A�悪40�_�A�ʐ^��12�_�B��Ƃ��Ăّ͊�1�_�A�l��3�_�̑��͂��ׂĉ������c���ꑺ�L�O���p���̏����B �P�D��������:�F�@�c���́A1926�N �����s�ŋ�̎Œ��w�Z�𑲋ƁB�Ⴍ���ē��i���n��j�ɍ˔\�����u�_���v�ƌĂꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B1926�N�ɓ������p�w�Z�i���{��ȁj�ɓ��w�B �����ɓ��R�@�A���{�����炪���邪�A���N6���ɒ��ނ��A�Ȍ����`���Ĉ�Ƃ̐��v�𗧂Ă��B���ꂪ�ނ́u��������v�ł���B �@���������āA���̎���̏o�W��i�͂��ׂē��B5�_�o�Ă������A�ނ̓��{��̑�z�����˔\����������Ă���B �Q�D��t����F�@1938�N�ɐ�t�ɕ�炷�悤�ɂȂ����B�u��t����v�ł���B 1947�N�ɂ͐�[���q��Â̐��W�ɓ��I�������A��[�ƈӌ������킸�A���Ђ�������ꂽ�B1955�N�̐����{�X�P�b�`���s���]�@�ƂȂ�A�����ւ̈ڏZ�����ӂ����B ���̎���̏o�W��i��19�_���������A���ꂼ��ɍ앗���قȂ�A�c���̉�Ƃ̕������ĂƂ��B�s��t���E���H�t�͒������l�����`����Ă����������B1955�N�ɋ�B�ŕ`���ꂽ�s�����@�t�͑f���炵���썑�̏�i�ŁA��������̍�i��\������B �R�D��������F�@1958�N�ɉ����哇�ɓn��A�哇�ۂ̐��F�H�Ő��v�𗧂ĊG��`���n�߂��B���̂Ƃ��ꑺ�A50�B�u��������v�̎n��ł���B5�N�����A3�N���`���A2�N�ŌW�̔�p���҂��Ƃ���10�N�v�悾�����B 1977�N69�Ŗv�B���̌�A���j���p���œc���ꑺ���Љ��Ĉȗ��L���ɂȂ����B���{�̃S�[�M�����Ƃ��Ă�Ă���B��Ƃ��Ă͂ނ���A��������\�[�����A�A�����ɂ����s���Ȃ��������\�[�ƈႢ���ۂɓ썑�ɏZ�̂������͂�S�[�M�������B ��������̑傫�ȍ�i�Ƃ��Ắs�C�ӂ̃A�_���t�̐F�ʂ������Ƃ���ۓI�������B���������Δނ̐��U��`�����f��u�A�_���v��������ɏ�f�����Ƃ̂��ƁB�s�����̓m�G�`�r���E�ƃu�[�Q���r���A�t��s�����̓m�C�`���Ԃƒ��t����◎���������F�ʂȂ���썑�I�B����قǑ傫�ȉ�ł͂Ȃ����s�M�ы��t�̐ԂƗ��N�����B
�S�D�ʐ^�F�@�ނ̎�ł������ʐ^�ɂ���ē썑�̐A����ގ��g�̎p��m�邱�Ƃ��ł����B �@���K�͂����A�c���ꑺ�̑S�e���T�ς���D�W����ł���B�ނ́u��͑��l�̂��߂ɕ`���̂ł͂Ȃ��B�����̂��߂ɕ`���̂��v�Ƃ����Ă����Ƃ����B������\�Y�ɒʂ��Ǎ��̉�ƁB �@�A��ɂ͑��̊X���m���r���U�������B�b�g��i�����܂���j�ɂ����ĕ����A�u�˓c���j�`�����v�ɂ�������B�w�܂ł́u�̖��ʂ�v�B�ӔN�A�̖������̒n�ʼn߂������Ƃ̂��ƁB�ǂ����p�U���������B (2006.10a) |
|
�@���̓��ʓW�̉��ɓ���Ƃ����Ȃ���t�́s���یQ�b�}�t���}���Ă����B���ʂ�6000�ȏ��1cm�̃}�X�ɋ敪���A���̃}�X���ƂɔZ�W2��ނ̊D�F���{���Ƃ����Â�悤�ł���B �@�u�}�X�ڕ`���v�Ƃ��Ă͐É��������p�ق�v���C�X�R���N�V�����̂��̂̂悤�Ȕh��ȐF�ʂł͂Ȃ��A���̂ق��͊D�F�ƒ��F�����Ƃ��������������F�ʂł���B�u�l�\�����E�S�l�v�Ƃ����a�̓`���F����Ȃ̂ł���B �@�G�ɕ`����Ă��铮���́A�ۂ̂ق��ɁA�i�فE�F�E2�C�̎蒷���E�I�l�Eꌂł���B�����͂��������Ȏp�����Ƃ��Ă���B�܂��ɍ]�˂̃}�j�G���X���I��z�̌n���B
�@�܂���F�̈�3�悳��Ă���A��ԉ��̂��̂͂͂�����Ɓs��t���m�t�Ɠǂݎ���B���������Ă��ꂪ��t�̍�i�ł��邱�Ƃ͋^�������Ȃ��B����ɂ���ׂ�Ɛ���ς��v���C�X�R���N�V�����́s���b�Ԗؐ}�����t�͂��̂悤�ȈȂ������łȂ��A�\�}���P���ł��邽�ߎ�t�̖{�삩�ǂ����ɂ��Đ��Ƃ̊Ԃňӌ�������Ă���B������ɂ��悱��̓z�����m�B�킴�킴���܂ŋ삯�����b�オ�������B �@���͓����̊G�ł��ӂ�Ă���B��t�ȊO�̗L����Ƃ̂��̂����Ȃ��Ȃ��B�T�H�E�����E�n���E����E��E����E�c��E����E���t�E�L���E�k�ցE�L�d�E���F�E���R�E�]���E�E�E�悭�����ꂾ���W�߂����̂ł���B �@�܂���1�́u������W���v�Ƃ��ğ��ϐ}�E�\��x�}������A���ő�2�͂��u������v�Ƃ��Ă܂Ƃ߂Ă������B�l�����䒼���A�����X�c��A�{���ɓ���t�A���������m�Ƃ����悤�ɂ����ӂ����܂��Ă����B������͂����g�ˉ�Ƃ��Ȃ��Ă����Ƃ̂��Ƃł���B�����ł͏\��x�̏��Ɉ���摜���ڂ��邱�ƂƂ���B���͓W����̂������悻�\��x�̏��ɕ��ׂ��Ă����B
�@���ɂ͑�3�́u�]�˂̃y�b�g����v�Ƃ��ĔL�ƌ��̊G�����߂��Ă���A����ɑ�4�́u�ӂ����ȓ��������v�Ƃ��Ē��b��d���̊G�⎑�����W�߂��Ă����B�����ɂ͑��̐������͓̉��E�l���E���̃~�C������Ă����B������ƑO�ɍ����Ȋw�����قŊς��u�������̕������W�v�Ɠ��f�ł���B�Ȃ�قǂ����͔��p�قłȂ������قł���B�Ō�ɑ�5�́u�������ɂ߂�v�Ŕ����w�̎���������Ă����B �@�قƂ�ǐ�`����Ă��Ȃ��W����ł��������A�ƂĂ��悩�����B���p�قƈႢ�A�L���v�V�����̐������Ȗ��B�}�^���R���p�N�g�ŁA���e�͕��Ղł���B��C�ɓǂݏI���邱�Ƃ��ł���B�ŋ߂̔��p�W�̌����āA�d���āA�����āA�����Đ�Ō�܂œǂނ��Ƃ̂ł��Ȃ����p�W�}�^�Ƃ͓V�n�̍��ł���B(2006.10a) |
| �҂��l�̊፷���u�w2006�v�@Vol�P ���F���w�[�����X�e�[�V�����M�������[
|
|
�@���̑�1�e�����w�ŊJ����Ă���B�s�약�A�c���M�s�A�����ׁA�ѕ��j��4�l�̃A�[�e�B�X�g�̗��̍�i���A�l���s�������A�ʉ߂���w��Ԃɐݒu����Ă���B �@���s�����قňɓ���t�̃}�X�ڕ`�̊G���ςɂ������łɁA�������i���ςČ����B�c���M�s�́s����t�B����ʂ�l�X�́u�i���_������H�I�u�W�F�H�v�Ǝ���������Ă���B�Ԃ��S���Ŏl�p�ɂ��ݏグ���^�̏��ɍ����l�p�`�̃K���X�炵�����̂��u����Ă���B�����̌��Ă���ʒu����͂���̌������ɃG�X�J���[�^�[�ƃg�C����������B��������荞��ŕs�v�c�ȃA�[�g�ƂȂ��Ă���B (2006.10a) |
|
|
|
����NHK�e���r���f���́u������Ƃ���]�ˊG��v�̂Ȃ��ɍ��F�������Ă���A���̃e�L�X�g�ɍڂ��Ă���G���������W������Ă���B�Ⴆ�s���������ْw偗d���}�t��s���s����̏��t�Ȃǂł���B�ق�Ƃ��ɗǂ��^�C�~���O�ł���B ���̑��́A���s�����́s�����̗��t�E�s�V�g���t�E�s��X�t�A�s���s�x�m���O�\�Z�i�@������̉��i�t�A�s���������������t�A�s���q��[�肨��v�ʁt�B (2006.10a) |
| �r�،o�ҁ\�����l���F�]�˓���������
|
|
���ʓW�����̈�́u�����l���v�B�Ⴋ���̐Ό��T���Y�̏Ί�A���D�ɐZ���������厡�̗��́A���{�����������O���R�I�v�̗��̂ȂǁA1960�N�ォ��2006�N�̍����܂ł̓����ɏZ�ސl�Ԃ̎p��ʂ��Ă݂�����j�B �S�̂Ƃ��Ă݂�A���̓W���̓A���[�L�[�̐l����Y�قɕ�����Ă���B �ʂȓW�����ɂ́u�����F���v�B�A���[�L�[�D�݂̍ʐF�ʐ^���邢�̓J���[�ʐ^�B�Ȃ��g�J�Q�����ɔ����Ă���ʐ^�������B�ϑԁB ���̂ق���ݓW�̂����������ǂɁu�F���v�A�u�������v�A�u�S��㇗��v�Ȃǂ��W������Ă���B�����͖���B������ɂ��悱�̂悤�ɖz���ȍ�i�\�ł���A�[�e�B�X�g�͍K�����낤�B (2006.10a) |
| �������̕������W�F�����Ȋw������
|
|
�����́u���{�ɐ������������������v�ł���B�V��E�͓��E�l���̃~�C������������o�Ă����B�V���ɂ��Ƃ����͓����̍��Ȃǂ𗘗p�����͌^�ł���Ƃ̂��Ƃł��邪�A�L���v�V�����ɂ͉��������ĂȂ��B���̂ق����q���̖����Ȃ��Ă����B�]�ˎ���ɂ́s�d���G���t�Ȃlj��������ނɂ�������╂���G�����삳��Ă��邪�A����͒�������̏�������ɂ������̂ł���A�������͓��{�݂̂Ȃ炸�����E�����ł����̑��݂��M�����Ă����Ƃ������Ƃ�������B �����́u�������̐i���v�ƂȂ��Ă���B���̎���ɂ͉������͎��݂̐������Ƃ��ĉȊw�̑ΏۂɂȂ��Ă����B�W�����ꂽ�����w�̎��������͂��̂悤�ȉȊw�̐i���̑��Ղł���B���̉��ɂ����c�ЕF�̊ܒ~�̂��錾�t���������Љ��Ă����B�u�K���Ȃ��ƂɁA�����������q���̍��ɂ́A�c�ɂɂ͂�������̉��������Z��ł����B�Ȋw�̖ړI�͎��ɉ�������{���������Ƃł���A���݂̉Ȋw����͐̂̉���������ɖ߂�K�v������B�v(2006.10a) |

 �@���߂Đ�菬�Ղ̊G���܂Ƃ܂��Č��邱�Ƃ��ł��܂����B�R����p�قő啪�O�Ɂs�ӂ邳�Ƃ̖��t�Ƃ��������w���e�B�b�N�ȑ傫�ȉ����������ł��B����͏����̑�a�G���̂��̂���A���m�I�ȑ�ނ̊G�ɕς���Ă����o�܂��悭������܂����B��a�G�Ƃ����Ă����Ղ̂͒W���F�ʂŃz�����J�����G�ł��B�����C�ɓ������̂́s�͌�t�Ƃ����G�ł��B2�l�̂��P���܂��͌���y����ł��܂����A��ՁA���A�肠�Ԃ�̎��G�̕\�����ƂĂ����A���ł��B
�@���߂Đ�菬�Ղ̊G���܂Ƃ܂��Č��邱�Ƃ��ł��܂����B�R����p�قő啪�O�Ɂs�ӂ邳�Ƃ̖��t�Ƃ��������w���e�B�b�N�ȑ傫�ȉ����������ł��B����͏����̑�a�G���̂��̂���A���m�I�ȑ�ނ̊G�ɕς���Ă����o�܂��悭������܂����B��a�G�Ƃ����Ă����Ղ̂͒W���F�ʂŃz�����J�����G�ł��B�����C�ɓ������̂́s�͌�t�Ƃ����G�ł��B2�l�̂��P���܂��͌���y����ł��܂����A��ՁA���A�肠�Ԃ�̎��G�̕\�����ƂĂ����A���ł��B
 �@�����āA���ꂼ��̐���ɊW�̂��鎖�ۂɂ��āA�̖��E�ʊy�E�k�ցE�L�d�璘���G�t���`���������G��Ŗ{���o�W����Ă���B���̂ق��g���ŗp�����Ă���������₽���~�A���q���Ŏg�p����Ă�������{���Ƃ����������╨���W������Ă���
�B
�@�����āA���ꂼ��̐���ɊW�̂��鎖�ۂɂ��āA�̖��E�ʊy�E�k�ցE�L�d�璘���G�t���`���������G��Ŗ{���o�W����Ă���B���̂ق��g���ŗp�����Ă���������₽���~�A���q���Ŏg�p����Ă�������{���Ƃ����������╨���W������Ă���
�B �@���l�Ő��t�E�������v�i1901-82�j�e�q���c��ł����u�������v�̍�i�Ȃ�тɓ���̓W���ł���B�����G�̕����ʼn�̎d�������ꂽ���������A����W������Ă���̂͒c��A�N���X�}�X�J�[�h�A�|�`�܁A��ЎD�A���[�ژ^�A�������A�}�b�`���x���Ȃǂ̓��p�i�ł���B���ʂȂ�̂Ă��Ă��܂��悤�Ȃ��̂ł��邪�A�����ɒ�Ă�����̂�����Ɨ��h�ȃA�[�g�ł���B�@
�@���l�Ő��t�E�������v�i1901-82�j�e�q���c��ł����u�������v�̍�i�Ȃ�тɓ���̓W���ł���B�����G�̕����ʼn�̎d�������ꂽ���������A����W������Ă���̂͒c��A�N���X�}�X�J�[�h�A�|�`�܁A��ЎD�A���[�ژ^�A�������A�}�b�`���x���Ȃǂ̓��p�i�ł���B���ʂȂ�̂Ă��Ă��܂��悤�Ȃ��̂ł��邪�A�����ɒ�Ă�����̂�����Ɨ��h�ȃA�[�g�ł���B�@ �@�c��ł͊��q�X�ǂ̗X�֕ی�PR�p�̂��̂����[�����X�Ŗʔ��������B�v����i�̍���s�[��[���}�����t�̗[����w�`�}�ɕς��A�l�Ԃ������āA�ォ��R�{�̃w�`�}���~��Ă��Ă���B���ꂼ��ɁA�u�e�̂܂�����A�q���̕ی��u�E�u���ƔN���A�V��̕�v�E�u�Ԃ��c���A������ی��v�Ə�����Ă���A���ɂ͏c�����Łu���q�X�ǁ@�d�b���l���v�Ɛ����Ă���B
�@�c��ł͊��q�X�ǂ̗X�֕ی�PR�p�̂��̂����[�����X�Ŗʔ��������B�v����i�̍���s�[��[���}�����t�̗[����w�`�}�ɕς��A�l�Ԃ������āA�ォ��R�{�̃w�`�}���~��Ă��Ă���B���ꂼ��ɁA�u�e�̂܂�����A�q���̕ی��u�E�u���ƔN���A�V��̕�v�E�u�Ԃ��c���A������ی��v�Ə�����Ă���A���ɂ͏c�����Łu���q�X�ǁ@�d�b���l���v�Ɛ����Ă���B �@�ϋq�͂���قǑ����Ȃ����A�g�勾�������Ă�������ƊςĂ���悤�Ȑl�������B�ނ̓��ӂƂ���،��ؔł͉��k�i���j�̖��ɂ������̂ł��邩���r�I�������B����ł������ɍז��ɒ��肱�܂�Ă���B���̃C���[�W�̑����͓Ƒn�I�E���z�I�E���w�I�ŁA�K���ȗV�т�����B
�@�ϋq�͂���قǑ����Ȃ����A�g�勾�������Ă�������ƊςĂ���悤�Ȑl�������B�ނ̓��ӂƂ���،��ؔł͉��k�i���j�̖��ɂ������̂ł��邩���r�I�������B����ł������ɍז��ɒ��肱�܂�Ă���B���̃C���[�W�̑����͓Ƒn�I�E���z�I�E���w�I�ŁA�K���ȗV�т�����B
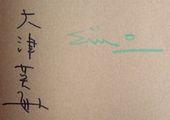 �@����܂⑹�ۃW���p�����������p�ّ�܂̎�҂ł���A���ݑ������p��w�̋��E�ɂ�����ł���B�������{�l�̃M�������[�E�g�[�N������Ƃ����̂ŎQ�������B
�@����܂⑹�ۃW���p�����������p�ّ�܂̎�҂ł���A���ݑ������p��w�̋��E�ɂ�����ł���B�������{�l�̃M�������[�E�g�[�N������Ƃ����̂ŎQ�������B









 �@�ÐF���R����r���̂T�K�̉��ɓ���ƁA6���̍L�������́u�Z���l�}�v���҂��Ă���B�n�̔Z�W���I�݂ł���B���l�̎������A��Ɠ��1�{�̑品�A�Q��2�{�̑品�A�l�͎���A�܂͂Ȃ�ƃ}�V�[���E�K���A�����ĘZ�͋|�B�p���͂��ꂼ��ɈقȂ�A���I�ł���B
�@�ÐF���R����r���̂T�K�̉��ɓ���ƁA6���̍L�������́u�Z���l�}�v���҂��Ă���B�n�̔Z�W���I�݂ł���B���l�̎������A��Ɠ��1�{�̑品�A�Q��2�{�̑品�A�l�͎���A�܂͂Ȃ�ƃ}�V�[���E�K���A�����ĘZ�͋|�B�p���͂��ꂼ��ɈقȂ�A���I�ł���B �@2�K�ɍ~���ƁA1�l������������锒���ʘH�������B�r���ɕ�꜂̂悤�ȏ�����������A�����̃J�[�e�����J����Ƃ����Ƌ����A�[�g���҂��Ă���B����������킢�ɔ����Ė��߂�҂��牽���̕��l�����ł���B���n�ڂ�AOKIT�𑫂���2�Ŋ������悤�Ȃ��̂ł���B
�@2�K�ɍ~���ƁA1�l������������锒���ʘH�������B�r���ɕ�꜂̂悤�ȏ�����������A�����̃J�[�e�����J����Ƃ����Ƌ����A�[�g���҂��Ă���B����������킢�ɔ����Ė��߂�҂��牽���̕��l�����ł���B���n�ڂ�AOKIT�𑫂���2�Ŋ������悤�Ȃ��̂ł���B �@�Ō�̕����ɓ���ƍ���̓W����̃_�C���N�g���[���̌��}�Ɠ��ƒւ̉Ԑ}���W������Ă����B���̕����ɎR����������ꂽ�̂ł��炭���b���������B�Z���l�}��B�������̕��l�Q�}�͎����̎��R�Ȕ��z���琶�܂ꂽ���̂������ł������B
�@�Ō�̕����ɓ���ƍ���̓W����̃_�C���N�g���[���̌��}�Ɠ��ƒւ̉Ԑ}���W������Ă����B���̕����ɎR����������ꂽ�̂ł��炭���b���������B�Z���l�}��B�������̕��l�Q�}�͎����̎��R�Ȕ��z���琶�܂ꂽ���̂������ł������B �@�ꌾ�ł����ƕ��i��W�B���������ꂾ���̓W��������O�̃R���N�V���������łł���̂�����A���n��̎��͂͐����B
�@�ꌾ�ł����ƕ��i��W�B���������ꂾ���̓W��������O�̃R���N�V���������łł���̂�����A���n��̎��͂͐����B �@�a�J�旧�������p�ق̂��̓W����͂��ł��ς���Ǝv���Ă�����ŏI���ɂȂ��Ă��܂����B
�@�a�J�旧�������p�ق̂��̓W����͂��ł��ς���Ǝv���Ă�����ŏI���ɂȂ��Ă��܂����B �@2004�N11���ɐ�z�s�����p�قŊJ����Ă����u
�@2004�N11���ɐ�z�s�����p�قŊJ����Ă����u �@���ʂ̐����ɗ������{�̑�i���}�j�́A���ŎO�p�`�̔������A���ł͍��E�ɐ���ɍL�����Ă���A�@���I�Ȋ��������o����B���Ă��̗��e�̉���͉��̂ق��͎R���̐F�ł��邪�A��O�̕��͓��X������e�ŁA���X����ꉹ���������Ă���悤�������B���ʂ̑��{���Ƃ���ƁA���E�̑�͘e���̂悤�ł���A���̕����S�̂������̖{���̂悤�Ɏv���Ă����B
�@���ʂ̐����ɗ������{�̑�i���}�j�́A���ŎO�p�`�̔������A���ł͍��E�ɐ���ɍL�����Ă���A�@���I�Ȋ��������o����B���Ă��̗��e�̉���͉��̂ق��͎R���̐F�ł��邪�A��O�̕��͓��X������e�ŁA���X����ꉹ���������Ă���悤�������B���ʂ̑��{���Ƃ���ƁA���E�̑�͘e���̂悤�ł���A���̕����S�̂������̖{���̂悤�Ɏv���Ă����B �P�D�@���������s�����V�����t
�P�D�@���������s�����V�����t �Q�D�ّ��s���������V�����t
�Q�D�ّ��s���������V�����t



 �T�D�����E�吳���̔��p
�T�D�����E�吳���̔��p![����]���Y�F���u](2006-5/ToshinSanpo0612/YasuiSotaroKinyo.jpg) 4�K�̓��W�R�[�i�[�́u����]���Y�v�ł���A�C�����ꂽ�s���u�t�A�s�������̟◬�t�A�s���R�����t�Ȃ�10�_���W������Ă����B����͎��̍D���ȉ�Ƃ̈�l�Ȃ̂ł�������Ɗӏ܂����B�ȑO������ƂȂ��Ă����s���u�t�̂Ђъ�����A����̏C���Ŗڗ����Ȃ��Ȃ��Ă����B
4�K�̓��W�R�[�i�[�́u����]���Y�v�ł���A�C�����ꂽ�s���u�t�A�s�������̟◬�t�A�s���R�����t�Ȃ�10�_���W������Ă����B����͎��̍D���ȉ�Ƃ̈�l�Ȃ̂ł�������Ɗӏ܂����B�ȑO������ƂȂ��Ă����s���u�t�̂Ђъ�����A����̏C���Ŗڗ����Ȃ��Ȃ��Ă����B �V�D�푈�L�^��
�V�D�푈�L�^��





 �@�ː��̒��͓�������͂Ȃ��Ȃ������B���t���a�ɗU���ĉ���7���Ԃ̉��o�������B�ߓ��͂��Ȃ�̍⓹�A�Ō�͂���ɋ}���z�̊K�i�B���p�َ��̂����̎R���@���Č`�ɂȂ��Ă���A5�K�������B���ɂ̓G���x�[�^�[���Ȃ��̂ő̗͏����B
�@�ː��̒��͓�������͂Ȃ��Ȃ������B���t���a�ɗU���ĉ���7���Ԃ̉��o�������B�ߓ��͂��Ȃ�̍⓹�A�Ō�͂���ɋ}���z�̊K�i�B���p�َ��̂����̎R���@���Č`�ɂȂ��Ă���A5�K�������B���ɂ̓G���x�[�^�[���Ȃ��̂ő̗͏����B �@�ǂ��m���Ă��邱�Ƃ����A��ݓW�ɑf���炵����i�������B
�@�ǂ��m���Ă��邱�Ƃ����A��ݓW�ɑf���炵����i�������B


 �@��1�́u�A�����J���V�[���̉�Ƃ����v�ł�20���I�����Ƀ��[���b�p����j���[���[�N�ɔ�����Ƃ̕č��̕�炵�����߂��i������ł����B�W�����E�X���[���́s��̑��Ӂt�̌����ƌ����̊Ԃɐ��������Ă����i��w9�|11�x��\������悤�ȃQ�I���O�E�O���X�́s�S�[���f���E�V�e�B�t����ۓI�������B
�@��1�́u�A�����J���V�[���̉�Ƃ����v�ł�20���I�����Ƀ��[���b�p����j���[���[�N�ɔ�����Ƃ̕č��̕�炵�����߂��i������ł����B�W�����E�X���[���́s��̑��Ӂt�̌����ƌ����̊Ԃɐ��������Ă����i��w9�|11�x��\������悤�ȃQ�I���O�E�O���X�́s�S�[���f���E�V�e�B�t����ۓI�������B




 �V���j���p�قŏЉ��Ă���
�V���j���p�قŏЉ��Ă��� �Q�D�\����`�I�G���i1945�`60�N��O���j
�Q�D�\����`�I�G���i1945�`60�N��O���j

![�O��̐�L���́s�]�˖����S�l�����@�Ԃ����X��t](2006-5/UKIYO-E/UKIYO-E%20003.jpg)
![�̐�L�d�́s�����]�˕S�i�@�ň����R�t](2006-5/UKIYO-E/UKIYO-E%20005.jpg)






![�L�d�́s�����]�˕S�i�@�ł���V���i�t](2006-5/UKIYO-E/UKIYO-E%20010-1.jpg)
![�L�d�́s�����]�˕S�i�@�������@�ʼnY�t](2006-5/UKIYO-E/UKIYO-E%20010-2.jpg)
![�O��L���́s�]�˖����S�l�����@�V�͂��t](2006-5/UKIYO-E/UKIYO-E%20011.jpg)
![�L�d�́s�]�˖����l�G�@�����̌i�t](2006-5/UKIYO-E/UKIYO-E%20012.jpg)
![�L�d�́s�]�˖����l�G�@�����̌i�t](2006-5/UKIYO-E/UKIYO-E%20013.jpg)


![���F�́s�����`�m�����V���@�����{�]�V�}�t](2006-5/UKIYO-E/UKIYO-E%20016.jpg)
![����t�͂̒��G�s���㒆�������@�H���S�o[�]��N��L]�t](2006-5/UKIYO-E/UKIYO-E-long.jpg)




 �@
�@
 �@�����̕����̓��B��t�s���p�قŊJ����Ă�����ʓW�u�Y��ʓ��v�̏����ցB���܂�ɂ��L���ȁs���_⿐�}�t�͍���W�ʼn�������ڂɂ������Ă���A���̂��тɕs�v�c�ȊG���ȂƎv���Ă����B����̓W����ɂ́A�W���ւ��͂�����̂́A����237�_���o�i�����Ƃ����B����͕��̂悢�@��Ǝv���ďo�������B
�@�����̕����̓��B��t�s���p�قŊJ����Ă�����ʓW�u�Y��ʓ��v�̏����ցB���܂�ɂ��L���ȁs���_⿐�}�t�͍���W�ʼn�������ڂɂ������Ă���A���̂��тɕs�v�c�ȊG���ȂƎv���Ă����B����̓W����ɂ́A�W���ւ��͂�����̂́A����237�_���o�i�����Ƃ����B����͕��̂悢�@��Ǝv���ďo�������B![�Y��ʓ��F�ۋ]�����E������ΐ}](2006-5/Uragami-Kokin.jpg) �@�W���́u���́v�Ɏn�܂�A��1�́u���R�ݏZ���𒆐S�Ɂv�A��2�́u��ƓW�J���v�A��3�́u���ƌ�F�v�A��4�́u���v�A��5�́u�s����v�A��6�́u�撟�v�A��7�́u���v�A��8�́u�����Ձv�Ƃ������ނł���B���߂͕��ނɏ]���ēW������Ă������A�r������͂������̕��ނ̍�i���܂Ƃ߂Ē�Ă���B�����̊W�Ȃ̂��낤���A��E���E���E�ՂȂǍL�����p�[�g���[�����Ȃ����ʓ��̓W���Ƃ��Ă͂��̂悤�ɟӑR��̂ƂȂ��Ă���̂��������ėǂ������B
�@�W���́u���́v�Ɏn�܂�A��1�́u���R�ݏZ���𒆐S�Ɂv�A��2�́u��ƓW�J���v�A��3�́u���ƌ�F�v�A��4�́u���v�A��5�́u�s����v�A��6�́u�撟�v�A��7�́u���v�A��8�́u�����Ձv�Ƃ������ނł���B���߂͕��ނɏ]���ēW������Ă������A�r������͂������̕��ނ̍�i���܂Ƃ߂Ē�Ă���B�����̊W�Ȃ̂��낤���A��E���E���E�ՂȂǍL�����p�[�g���[�����Ȃ����ʓ��̓W���Ƃ��Ă͂��̂悤�ɟӑR��̂ƂȂ��Ă���̂��������ėǂ������B �@�ςȊ��z���ɏ����Ă��܂������A���C�ɓ����������ƁA�s�Վʊ���}�t�E�E�E��w�̕����I�݂ɕ\������Ă���A�s�H�R�ӎސ}�E�ꏑ�앗�́t�E�E�E�����ɒ���ꂽ�L���[�g�ȏ��i�A�s�R�J���}�t�E�E�E���F�ƗōʐF���ꂽ��������ʁA�s�����_�ݐ}�t�E�E�E�̔��������i�A�s�R絓Ǐ��}�t�E�E�E��[�N�����~�J���Ɋ|�����J�ɉ��ގR�i�A�s�[�ѐ�ǐ}�t�E�E�E���|�I�Ȕ��͂̏d�v���p�i�A�s�R�J���ߐ}�t�E�E�E�o�����X�̂悢���i�A�s�k�������}�t�E�E�E�Y�ӂȒ�����̗ї��I�A�s�R���撟�t�E�E�E�S�n�悢�_�炩�ȋȐ����A�s�������t�̐R�g�ѐ}�t�E�E�E���ސF�̍g�t���f���炵���d�v�������B
�@�ςȊ��z���ɏ����Ă��܂������A���C�ɓ����������ƁA�s�Վʊ���}�t�E�E�E��w�̕����I�݂ɕ\������Ă���A�s�H�R�ӎސ}�E�ꏑ�앗�́t�E�E�E�����ɒ���ꂽ�L���[�g�ȏ��i�A�s�R�J���}�t�E�E�E���F�ƗōʐF���ꂽ��������ʁA�s�����_�ݐ}�t�E�E�E�̔��������i�A�s�R絓Ǐ��}�t�E�E�E��[�N�����~�J���Ɋ|�����J�ɉ��ގR�i�A�s�[�ѐ�ǐ}�t�E�E�E���|�I�Ȕ��͂̏d�v���p�i�A�s�R�J���ߐ}�t�E�E�E�o�����X�̂悢���i�A�s�k�������}�t�E�E�E�Y�ӂȒ�����̗ї��I�A�s�R���撟�t�E�E�E�S�n�悢�_�炩�ȋȐ����A�s�������t�̐R�g�ѐ}�t�E�E�E���ސF�̍g�t���f���炵���d�v�������B



 �@
�@











![���c���]�F�Q���}](2006-5/111Inu150.jpg)


 �@�����w�ԗ����w�ɂ̕����H���ɔ����A�����X�e�[�V�����M�������[��5�N�ԋx�فB���̊Ԃ������{�S���������c�͔��p�ي����𑱂���B
�@�����w�ԗ����w�ɂ̕����H���ɔ����A�����X�e�[�V�����M�������[��5�N�ԋx�فB���̊Ԃ������{�S���������c�͔��p�ي����𑱂���B �@�]�˓������p�ق̏�ݓW�A�u�]�˂̔��v�̕����G�R�[�i�[�ɂ͍��F�̔ʼn悪8�_�łĂ����B
�@�]�˓������p�ق̏�ݓW�A�u�]�˂̔��v�̕����G�R�[�i�[�ɂ͍��F�̔ʼn悪8�_�łĂ����B �����]�˔����قł�
�����]�˔����قł� �U���Ďv�������Ȃ��W����������Ȋw�����قŊς��B
�U���Ďv�������Ȃ��W����������Ȋw�����قŊς��B