創造の広場 イタリア展 07.5 |
パルマ展 07.5 |
プラハ国立美術館展 07.5 |
モーリス・ユトリロ展 07.6 |
アンドリュー・ワイエス展 07.6 |
ロマネスク美術写真展 07.7 |
松岡美術館 07.7 |
キスリング展 07.7 |
トプカプ宮殿の至宝展 07.8 |
槐安居コレクション展(前期) 07.8 |
景徳鎮千年展 07.8 |
アルフレッド・ウォリス 07.8 |
秘蔵の名品アートコレクション 07.8 |
アジアへの憧憬 07.8 |
都市のフランス 自然のイギリス 07.8 |
槐安居コレクション展(後期) 07.8 |
| ヴェネツィア絵画のきらめき 07.9 | インドの細密画(2) 07.8 | フェルメール 07.9 | モリゾー 07.9 |
| シュルレアリスム 07.9 |
目 次 ↑
|
開催初日に観に行った。ちょうど開会式で館長の挨拶中。宇都宮美術館・豊田市美術館・横浜美術館の共同開催展とのこと。アンドレ・マッソン夫人が出席されていた。偶然そこへlysanderさんが現れたので、一緒にこの企画展と常設展をゆっくり観た。幸いどちらも空いていたので、われわれのおしゃべりもあまり迷惑にならなかったかとおもう。
中心となる第2章では、1)イメージが訪れる、2)反物語、3)風景、4)女と愛、5)物と命、6)神話と魔術、7)時空の彼方に、の7節に細分しているが、この分類によって鑑賞者の理解が助けられるといったものではなかった。そのため、一つ一つの作品の面白さを個別に楽しんでいくようになってしまった。 メモや記憶に残っているのは、そのごく一部。マッソンの小品《血の涙》は、2つの人物のようなイメージの間に小さな真赤な涙が描かれていた。個人蔵となっていたので、マッソン夫人が所蔵しておられるものではないかと勝手に考えた。オスカル・ドミンゲスのデカルトマニ-の《日曜日》という作品では、画面中央左の草のような緑のイメージが残像となっている。エルンストの《カルメン会》の黒いマントをかぶった修道僧、イヴ・タンギーの《失われた鏡》、エルンストの《子供のミネルヴァ》、ロベルト・マッタの《ハート・プレーヤー》、ダリの《ガラの測地学的肖像》、ダリの三部作《暁(ヘレナ・ルビンシュタインのための壁面装飾「幻想的風景」)》、《英雄的な昼(ヘレナ・ルビンシュタインのための壁面装飾「幻想的風景」) 》、《夕暮(ヘレナ・ルビンシュタインのための壁面装飾「幻想的風景」) 》などは印象的な作品で、lysanderさんとそれぞれの感想を語り合った。 絵はがきを買ってきたのはマッソンの《ナルキッソス》の一枚だけ。陸上の下半身と水面を覗き込んでいる上半身が表裏逆の姿としてイメージされている。神話のエコーと水仙の花も描かれている。 常設展では、ミロとデルボーの版画、シュールリアリスムと写真、カンジンスキー/ミュンターの作品の並列展示など前回と同じだったが、同行者がいると話が弾み、写真を撮ったりして楽しんだ。 (2007.9a) ブログへ |
|
「本邦初のモリゾ展」となっているが、1995年に伊勢丹美術館で開かれた「印象派の華 モリゾ・カサット・ゴンザレス展」の図録を見ると、今回の展示作品が少なからず載っている。 それはともかくモリゾは、フラゴナールの末裔、コローの弟子、マネのモデル、マネの弟ウジェーヌの妻、ジュリーの母、そして印象派展の優等生、マラルメやポール・ヴァレリーのサポートなど話題に事欠かない。 しかし肝要なことは女性が一人で外出することさえはばかれた時代に、女性画家として一家を成し、現代までその名を残していることである。 幸い、学芸員のギャラリー・トークに参加できたので、理解が進んだ。17歳の時にルーブルで模写した《ヴェロネーゼの磔刑》はうまい。学芸員が見せてくれたヴェロネーゼの画とそっくり。模写では下から見上げて描くため、その修正が必要であるが、その点立派に描けている。やはり画の才能に恵まれている。《モリクールのリラの木》は1874年の作品。姉のエドマの家族。丁寧に描かれた美しい作品である。手前の帽子と日傘はモリゾ自身のものであるとの説明である。 《淡いグレーの服を着た若い女性》や《スケート靴を履きなおす若い女性》は、少ないタッチで描かれており、未完成のように見えるが、モリゾはこのような画風になってきているのである。 《砂遊び》や《庭のウジェーヌ・マネと娘》などは、太い筆を使った荒々しいタッチの画である。《寓話》は娘ジュリーとメイドのパジー。自由ですばやいタッチで、全体の印象をとらえている。 《桜の木》にはいくつものヴァージョンがあるが、これは油彩の第1ヴァージョン。ルノワールの影響を受けているとの説明だった。《水浴》は女性画家にしては珍しいヌード。ルノワールの傍で描いたということであるが、肉体の官能性はまったくなく、モリゾ自身の個性とオリジナリティは失われていない。
《夢見るジュリー》は少女から女性に変身してゆく娘を眺めている。この画を描いた翌年モリゾは娘の風邪がうつって死亡した。その後、ジュリーの後見役となったマラルメの言葉によると、「彼女の早すぎた死は美術に大きな空白を残した」。 姉エドマがモリゾを描いた大きな油彩、モリゾがドガの助けを得て作った《ジュリーの胸像》、そしてジュリーの姿が描かれたモリゾのパレットなど家族愛あふれる作品がこの展覧会の質を高めていた。 (2007.9a) ブログへ |
|
アムステルダム国立美術館が改装中ということで来日した「ミルク・メード」はわたしの西洋美術開眼に大きな影響があったので思い入れがある。 展示は以下の6部門に分類されていた。 1.「黄金時代」の風俗画: 油彩画は台所・室内・行商・飲酒などと主題によって細分されているが、小品で暗い風俗画が多い。隠喩や寓意が含まれているものも少なくない。当時の状況がそうであったのだからいたし方ないが、なんとなく清潔感に欠ける画が多い。ヤン・ステーンのものが多かった。その他にメツー、テル・ボルフ、マースの作品が出ていた。次いで版画がたくさん出てくる。ヤーコブ・マーダムの《聖書と主題のある台所と市場》の連作では、一番奥に「エマオの晩餐」のような聖書の一場面の画が掛かっている。とてもうまい画であるが、これらを観るには単眼鏡が絶対に必要。
3.工芸品・楽器: ヨハネス・リュトマ2世の《聖杯》に目がいった。杯の脚に天使・獅子・牡牛・鷹といったマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネのアトリビュートが乗っていた。 古楽器が並べられたコーナーの奥の部屋は《牛乳を注ぐ女》がいたと思われる台所となっており、その手前の部屋はヴァージナルなど楽器が描きこまれた部屋のようなタイル床となっていた。古楽器は上野学園のコレクションとのことである。 4.版画と素描: レンブランド、ファン・オスターデ、ボルなどの有名画家の作品も含まれていたが、いずれも小品だった。 5.偉大なる17世紀の継承と模倣: 似たような作品を集めて、オランダ風俗画が連綿とつながっていく様が示されていた。全体としては「黄金の時代」の作品より明るくなり、またその分軽くなっているように思われた。 6.19世紀後半のリアリズム風俗画: ヨーゼフ・イスラエルスの《小さなお針子》や、マリスの《窓辺の少女》の愛らしさ、ウェイセンブルッフの《ハーグの画家の家の地階》の逆光、デル・ヴァーイの《アムステルダムの孤児院の少女》の美しさなど、この章にはお気に入りの作品が多かった。 (2007.9a) ブログへ (追記)フェルメール・オフ会: ミルクメイドは前より見やすくなっていた。細かい点を見直した。大勢の参加者。出席者多数+Tak2, toshi2, Nikki, KAN, mizdezign, merion, ruru,panda, Luo とら、はろるど、わん太夫、さちえ、きのこ、タッキー&ササキ、朱奈、一村雨、とんとん、ともすみと・・・。 (2007.11a) ブログへ |
|
ムガル王朝時代(15-19世紀)のインド細密画は有名である。今回は60点を前期・後期に分けて陳列してあるが、わたしの観たのは前期である。今年の1月にも展示されていたが、よく見るとなかなか味がある。写真はフラッシュがないので鮮明度が悪いが、実物を観るととても美しい。主題はマハーバラタやラーマヤナといった神話、ヒンドゥー世界のシヴァ神やヴィシュヌ神、王・恋・動物・音楽などさまざまである。
お気に入りの画像を10枚アップする。
(2007.8a) ブログへ |
|||||||||||||||||||||||||
|
第1章 宗教・神話・寓意 ティツィアーノの《洗礼者聖ヨハネの首をもつサロメ》は有名な画。もちろんこの展覧会のポスターにもなっている。なんといってもサロメの顔が美しく、巻き毛もきれい。そして衣装の赤い色彩が際立っている。洗礼者聖ヨハネの首はティツィアーノの自画像という説があるそうだが、なるほどそのようにも見える。 ヴェロネーゼの《エッケ・ホモ》はこの巨匠の晩年の傑作とされているが、色使いと大胆な筆致が特徴的である。 ティントレットの《愛の始まりの寓意》やジョルダーノの《ギリシャの哲学者》も良かった。 ヨーゼフ・ハインツという画家は初めて知ったが、《アイソンを若返らせるメディア》は、まるでボスのようなおどろおどろしい画。《パリスの審判》はよくある神話がだが、都市景観画家のグアルディのものは珍しい。 ティエポロの《聖母子と聖フィリッポ・ネーリ》は小さな油彩小銅版であるが、きちんとした画で好感が持てる。ピエトロ・ロンギの画が沢山あったが、なかでは当時の田舎の情景を描いた《糸巻きをする女》などはよいとして、華やかなロココ的な生活の画はあまり好きになれない。 第2章 統領のヴェネツィア 第3章 都市の変貌 ガブリエル・ベッラ(1730-99)という画家の大きな風景画が10点揃って出ていた。カナレットやベロットにくらべれば荒削りだが、その分、素朴な画であるともいえる。そのなかで一番面白かったのは《教区司祭の入場、サンタ・マルゲリータ広場》で、謝肉祭最後の木曜日の広場の情景。大きな山車、人間ピラミッド、滑車ロープで花を司祭に届ける男などが見せ場。 このようにして、しばしの間「アドリア海の真珠」といわれる水の都ヴェネツィアの全盛期を楽しむことができた。 (2007.9a) ブログへ |
|
「18・19世紀絵画と挿絵本の世界」いう副題がついている。改装中の栃木県立美術館の代表的な西洋絵画と豊かな版画コレクションの紹介である。 1.フランス絵画 2.フランスの版画・挿絵本 一方、貴族社会を描いたヴァトーの雅宴画エッチング《滝》・《嫉妬深い者たち》・田園の遊楽》はいかにもロココ的な情景であり、ロマン派の代表者ドラクロアのリトグラフ《ハムレット》はきわめて動的な版画であった。
3.イギリスの絵画
4.イギリスの版画・挿絵本
(2007.8a) ブログへ |
|
1.タイ: アユタヤ朝は14-18世紀まで長期間続いたが、その中で今回出ていたのは、16-17世紀の ≪仏陀立像≫、≪仏陀坐像≫、≪宝冠仏立像≫と19世紀のラッタナコーシン朝の≪宝冠仏立像≫が2点、≪仏弟子坐像≫、≪釈迦牟尼立像≫。 この時代の仏像は、大量生産され、宝冠を被り身体中に装身具をつけた宝冠仏や台座に豊かな装飾を施した仏像など形式化と装飾化が進んだものであるといわれている。 2.ミャンマー: 19世紀のものではあるが、右側臥位の美しい≪横臥仏像≫があった。 3.ネパール: ヒンドゥー教の主神の一人の≪ヴィシュヌ立像≫で、やはり19世紀のものだった。 4.インド: 10-11世紀のパーラ朝の≪宝冠仏坐像≫、≪観世音菩薩立像≫など合計7点が出ており、勉強になった。形式的には、ヒンドゥー教へ接近しているものが少なくないと思われた。 5.朝鮮: 14世紀の高麗時代の≪阿弥陀如来三尊像≫と16世紀李朝の≪釈迦如来及諸聖衆像≫はとても美しかった。やはり日本の仏教に一番近い。 (2007.8a) ブログへ |
|
エコノミック・アニマル時代の日本企業は美術品を資産として買い込んでいたが、次第にこれを公開して入場料を稼ぐようになった。1991年に庭園美術館で開かれた「企業コレクションによる世界の名作展」を観た時には、このような企業の姿勢に疑問を抱いたことをホームページに書いている。 「アートは世界のこどもを救う」というキャッチフレーズの「企業の名品アートコレクション展」が最初に開かれたのは、1996年。ホテルオークラ開業35周年記念チャリティイベントだった。その展覧会には、特別出品として皇太后陛下の「仔兎」も出品されていたこともチャリティー展としての価値を高めていた。同様に、1997
年にBUNKAMURAで開かれた「コーポレート・アート・コレクション展」は長野オリンピックの組織委員会の主催となっていたので、その公共性ははっきりしていた。 さて今回の「第13回展覧会」の副題は1996年の「第1回展覧会」と同じく「チャリティーイベント アートは世界のこどもを救う」となっている。ただしいつのまにか「企業の名品」が「秘蔵の名品」に変わっている。これはバブルの崩壊と格差の増大に基づいて、個人所蔵家の重要性が増してきたからなのだろう。 今回の展覧会には、1.西洋絵画、2.日本画、3.洋画の3ジャンルから103点に及ぶ優品が出ていた。
(2007.8a) ブログへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 この企画展は、第1章「シュルレアリスムの胎動」、第2章「シュルレアリスムが開くイメージ」、第3章「シュルレアリスム以後の様々なイメージ」となっているように、マグリット・デルヴォー・ダリ・ベルメール・ミロ・マッソン・マッタ・エルンスト・ドミンゲスなどの狭義のシュルレアリスムだけでなく、その前駆をなすデ・キリこの形而上絵画、アルプ・シュヴィッタース・マン=レイ・デュシャンなどダダ、さらに広告美術、アンフォルメル、抽象表現主義、戦後具象絵画、現代日本美術まで非常に幅広くとらえている。
この企画展は、第1章「シュルレアリスムの胎動」、第2章「シュルレアリスムが開くイメージ」、第3章「シュルレアリスム以後の様々なイメージ」となっているように、マグリット・デルヴォー・ダリ・ベルメール・ミロ・マッソン・マッタ・エルンスト・ドミンゲスなどの狭義のシュルレアリスムだけでなく、その前駆をなすデ・キリこの形而上絵画、アルプ・シュヴィッタース・マン=レイ・デュシャンなどダダ、さらに広告美術、アンフォルメル、抽象表現主義、戦後具象絵画、現代日本美術まで非常に幅広くとらえている。 1889年の《ブ^-ロニューの森の湖》は、画はその中央の大きな木によって左右に分断されている。これは浮世絵の影響であり、事実モリゾはカサットと一緒に浮世絵展にいっており、今回の展覧会にはそのカタログも出品されていた。この画のもう一つの特徴として、湖面に映る影の描写があげられる。これはその後モネに影響を与えただけでなく、抽象絵画のさきがけだったとも考えられるという。
1889年の《ブ^-ロニューの森の湖》は、画はその中央の大きな木によって左右に分断されている。これは浮世絵の影響であり、事実モリゾはカサットと一緒に浮世絵展にいっており、今回の展覧会にはそのカタログも出品されていた。この画のもう一つの特徴として、湖面に映る影の描写があげられる。これはその後モネに影響を与えただけでなく、抽象絵画のさきがけだったとも考えられるという。 2.フェルメール《牛乳を注ぐ女》: なんといっても、これがこの展覧会のハイライト。その前は結構込み合っている。画面と観客の間に2メートル以上の間隔があり、それ以上近づけない仕組みになっている。持ってきた単眼鏡が役立ち、パンの光沢・ミルクの輝き。壁の釘・金属の容器に映る窓枠、足元のデルフトタイルなど各部分は見ることができた。遠近法の集合点、後で消されたとおもわれる地図や牛乳壷、机の形が矩形ではないことなどの説明もあった。この画は、フェルメールの中では《青いターバンの女》と1、2を争う作品であるが、わたしはミルク・メードのほうに軍配を挙げている。こちらのほうが先に刷り込まれたためかもしれない。
2.フェルメール《牛乳を注ぐ女》: なんといっても、これがこの展覧会のハイライト。その前は結構込み合っている。画面と観客の間に2メートル以上の間隔があり、それ以上近づけない仕組みになっている。持ってきた単眼鏡が役立ち、パンの光沢・ミルクの輝き。壁の釘・金属の容器に映る窓枠、足元のデルフトタイルなど各部分は見ることができた。遠近法の集合点、後で消されたとおもわれる地図や牛乳壷、机の形が矩形ではないことなどの説明もあった。この画は、フェルメールの中では《青いターバンの女》と1、2を争う作品であるが、わたしはミルク・メードのほうに軍配を挙げている。こちらのほうが先に刷り込まれたためかもしれない。
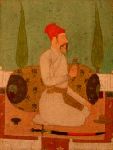
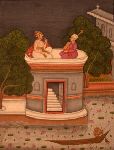

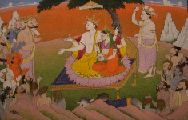


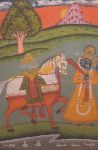
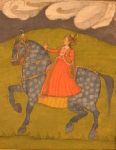

 ヴェネツィアの絵は明るくて、色彩豊かである。観ているものが幸せになる。初日のためか観客はちらほらだったが、そのうちきっと混んでくるだろう。
ヴェネツィアの絵は明るくて、色彩豊かである。観ているものが幸せになる。初日のためか観客はちらほらだったが、そのうちきっと混んでくるだろう。 1559年にジャック・カロが生まれたナンシーは当事ロレーヌ公国の首都だったが、1960年代に30年戦争によるフランス軍の侵攻を受けている。これをテーマにした《戦争の惨禍(小)》は6点組で、
1559年にジャック・カロが生まれたナンシーは当事ロレーヌ公国の首都だったが、1960年代に30年戦争によるフランス軍の侵攻を受けている。これをテーマにした《戦争の惨禍(小)》は6点組で、 本展のポスターになっているコンスタブルの《デダムの谷》はどこかで見たことのあるきがする作品である。図録によると、同一テーマの作品が他に2点あるとのこと。1点はスコットランド国立美術館、もう一点はV&A美術館。これら3点はいずれもクロード・ロランの《ハガルと天使》(ロンドン。ナショナルギャラリー蔵)にヒントをえたものだとのことである。
本展のポスターになっているコンスタブルの《デダムの谷》はどこかで見たことのあるきがする作品である。図録によると、同一テーマの作品が他に2点あるとのこと。1点はスコットランド国立美術館、もう一点はV&A美術館。これら3点はいずれもクロード・ロランの《ハガルと天使》(ロンドン。ナショナルギャラリー蔵)にヒントをえたものだとのことである。 久し振りで大倉集古館に行き、北魏の巨大な≪如来立像≫や平安時代「円派」の≪普賢菩薩騎象像≫に再会した。今回の「アジアへの憧憬」に展示物の中心は、いつものように中国のものであるが、それ以外の国の仏像・仏画がいくつか出ていることが目を惹いた。ただし、数が少なく、比較的新しいものが多いため、このような地域の仏教美術を俯瞰することは出来なかった。
久し振りで大倉集古館に行き、北魏の巨大な≪如来立像≫や平安時代「円派」の≪普賢菩薩騎象像≫に再会した。今回の「アジアへの憧憬」に展示物の中心は、いつものように中国のものであるが、それ以外の国の仏像・仏画がいくつか出ていることが目を惹いた。ただし、数が少なく、比較的新しいものが多いため、このような地域の仏教美術を俯瞰することは出来なかった。
 イギリスのアルフレッド・ウォリス(1855-1942)は、若い頃船乗りの生活をしていたが、その後港町セント・アイヴィスで船具商を営み、70歳になってから独学で画を描きはじめた。いわばグランマ・モーゼスの男性版である。 ボール紙や板の切れ端に油彩やペンキで描いたもので、この点でもグランマ・モーゼスに通う素朴画家である。テーマとしては、港・船・橋・灯台といった海に関わるものが多く、この美術館にピッタリの海の素朴画家である。大胆な俯瞰図や斜めの構図など、独学であるがゆえの新鮮さを感じられる画も少なくない。お気に入りのベストは、≪緑の野原の側を横切るブリガンティーン≫。緑の色調が何ともいえない。
イギリスのアルフレッド・ウォリス(1855-1942)は、若い頃船乗りの生活をしていたが、その後港町セント・アイヴィスで船具商を営み、70歳になってから独学で画を描きはじめた。いわばグランマ・モーゼスの男性版である。 ボール紙や板の切れ端に油彩やペンキで描いたもので、この点でもグランマ・モーゼスに通う素朴画家である。テーマとしては、港・船・橋・灯台といった海に関わるものが多く、この美術館にピッタリの海の素朴画家である。大胆な俯瞰図や斜めの構図など、独学であるがゆえの新鮮さを感じられる画も少なくない。お気に入りのベストは、≪緑の野原の側を横切るブリガンティーン≫。緑の色調が何ともいえない。 「景徳鎮窯」は、北宋時代の景徳元年(1004年)の年号から名付けられたものであるが、青白磁の完成により有名になり、元時代には青花磁器、明時代には五彩磁器が作られるようになった。明清には宮廷の用を務める官窯となり「景徳鎮」の名前は世界的に有名になった。
「景徳鎮窯」は、北宋時代の景徳元年(1004年)の年号から名付けられたものであるが、青白磁の完成により有名になり、元時代には青花磁器、明時代には五彩磁器が作られるようになった。明清には宮廷の用を務める官窯となり「景徳鎮」の名前は世界的に有名になった。 明代の絵画としては、孫克弘の≪寒山拾得図≫がはっきりとした輪郭と明るい朱色がなかなか良い。
左図の
明代の絵画としては、孫克弘の≪寒山拾得図≫がはっきりとした輪郭と明るい朱色がなかなか良い。
左図の
 今回は一番すごいのは、巨大エメラルドのついた「ターバン飾り」。ダイヤモンドも沢山ついており、本当に光り輝いている。エメラルドを良く見ると、深い緑の部分が明るい緑の部分のなかに流れ込んでいる。
もう一つは、左図の「金のゆりかご」。木製だが、全面が金で覆われ、約2000個の宝石が埋め込まれている。これはトルコ政府が、秋篠宮家の悠仁親王の誕生を祝して、特別に貸し出してくれた秘蔵品である。
今回は一番すごいのは、巨大エメラルドのついた「ターバン飾り」。ダイヤモンドも沢山ついており、本当に光り輝いている。エメラルドを良く見ると、深い緑の部分が明るい緑の部分のなかに流れ込んでいる。
もう一つは、左図の「金のゆりかご」。木製だが、全面が金で覆われ、約2000個の宝石が埋め込まれている。これはトルコ政府が、秋篠宮家の悠仁親王の誕生を祝して、特別に貸し出してくれた秘蔵品である。
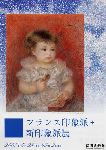 今回、この新美術館を初訪問してみると、随分立派な建物に変身している。庭も、隣の自然教育園を借景しながら素晴らしい。1階には、古代オリエント美術、現代彫刻(ムーア、グレコ、ブールデル)、ガンダーラ・インド彫刻(お気に入りは、仏陀の一生の彫刻)の常設展。2階は1年に数回コレクションを入れ替えて企画展としているようで、今回はフランス印象派・新印象派(お気に入りは、ブーダン《海・水先案内人》、モネ《エトルタの波の印象》、ルノワールの3点、ピサロ、ギョマン、シニャック、マルタンの3点)の企画展となっていた。面白かったのは、ルノワールの《リュシアン・ドーデの肖像》が床の間仕立ての部屋に飾られていたことである。
今回、この新美術館を初訪問してみると、随分立派な建物に変身している。庭も、隣の自然教育園を借景しながら素晴らしい。1階には、古代オリエント美術、現代彫刻(ムーア、グレコ、ブールデル)、ガンダーラ・インド彫刻(お気に入りは、仏陀の一生の彫刻)の常設展。2階は1年に数回コレクションを入れ替えて企画展としているようで、今回はフランス印象派・新印象派(お気に入りは、ブーダン《海・水先案内人》、モネ《エトルタの波の印象》、ルノワールの3点、ピサロ、ギョマン、シニャック、マルタンの3点)の企画展となっていた。面白かったのは、ルノワールの《リュシアン・ドーデの肖像》が床の間仕立ての部屋に飾られていたことである。 11世紀から12世紀にかけて生まれたロマネスク美術は、キリスト教の教えを広めるため、人里はなれた修道院や村の聖堂にまで展開されたもの。数年前にバルセロナの「
11世紀から12世紀にかけて生まれたロマネスク美術は、キリスト教の教えを広めるため、人里はなれた修道院や村の聖堂にまで展開されたもの。数年前にバルセロナの「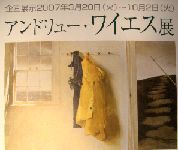 青山ユニマット美術館では、3‐4
階はシャガールなどエコール・ド・パリの常設展で、2階だけは企画展に使われている。
青山ユニマット美術館では、3‐4
階はシャガールなどエコール・ド・パリの常設展で、2階だけは企画展に使われている。 ユトリロの展覧会は何回も観ている。今回はパスしようかとも思っていたが、実際に行ってみると非常に良かった。
ユトリロの展覧会は何回も観ている。今回はパスしようかとも思っていたが、実際に行ってみると非常に良かった。 第1章 ブリューゲルの遺産
いきなりヤン・ブリューゲル(子)の《東方三博士の礼拝》。板絵の小品であるが、素晴らしい色合いが残っている。大切な作品らしく、ガラスで囲われている。隣のピーテル・ブリューゲル(子)の同名の画は、冬のフランドルに場所を移して描いているが、聖母子はなぜが画の右端にやっと見える程度である。
第1章 ブリューゲルの遺産
いきなりヤン・ブリューゲル(子)の《東方三博士の礼拝》。板絵の小品であるが、素晴らしい色合いが残っている。大切な作品らしく、ガラスで囲われている。隣のピーテル・ブリューゲル(子)の同名の画は、冬のフランドルに場所を移して描いているが、聖母子はなぜが画の右端にやっと見える程度である。 第3章 ルーベンスの世界ーキリスト教
第3章 ルーベンスの世界ーキリスト教 》は堂々たる肖像画である。ヴァン・ダイクの《オラニエ公ウィレム二世の少年期の肖像》はわたしのお気に入り。ポストカードを買った。
》は堂々たる肖像画である。ヴァン・ダイクの《オラニエ公ウィレム二世の少年期の肖像》はわたしのお気に入り。ポストカードを買った。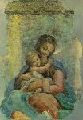 『パルマ派』の創始者
『パルマ派』の創始者
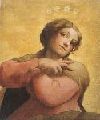 カラッチ一族の作品が5点もでている。
カラッチ一族の作品が5点もでている。